【2025年版】CSRD(企業サステナビリティ報告指令)とは?適用時期やダブルマテリアリティをわかりやすく解説

CSRD(企業サステナビリティ報告指令)と聞いて、「EU企業の制度だから日本企業には関係ない」と思っていませんか。日本企業でもEUでの売上額や取引関係によっては対象となるため、早急な対応が必要です。
本記事では、CSRDの概要、適用時期やダブルマテリアリティ、対応手順などをわかりやすく解説します。読めば、自社が取るべき具体的な行動が明確になります。
CSRD(企業サステナビリティ報告指令)とは

CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)とは、2023年にEU(ヨーロッパ連合)が発効した新たな指令で、企業に環境、社会、ガバナンス(ESG)に関する情報を詳細に報告することを義務づけたものです。
従来のNFRD(Non-Financial Reporting Directive)を改正したもので、対象企業が大幅に増え、報告内容も細かく規定されました。
CSRDは、2019年に発表された「European Green Deal(欧州グリーンディール)」の一環として導入され、2050年までに持続可能な経済成長を達成することを目指しています。
企業に温室効果ガスの削減をはじめとするサステナビリティや非財務的な活動を開示されることで、投資家や取引先、消費者などが、企業のサステナビリティを正確に把握し、より持続可能な経済活動への投資を判断できるようになります。
参照:JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)|CSRDをめぐる最近の動向
参照:JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)|CSRD 適用対象日系企業のためのESRS 適用実務ガイダンス
参照:ESGグローバルフォーキャスト|企業サステナビリティ報告指令(CSRD)
参照:日本総研|企業サステナビリティ報告指令(CSRD)・欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)の概要および日本企業に求められる対応
参照:EEAS|欧州委員会、脱炭素と経済成長の両立を図る「欧州グリーンディール」を発表
NFRDとCSRDの違い

NFRD(非財務情報開示指令)とは、2014年にEUによって導入された指令です。CSRDと同様に企業に対して、環境、社会、従業員関連、人権、反汚職、贈収賄などに関する財務以外の情報の開示を義務づけました。
CSRDには、対象範囲の拡大や報告基準の必要性、情報開示の形式など、NFRDで生じた問題点を解決した内容が盛り込まれています。
ここでは、NFRDと比較しながらCSRDの特徴を解説します。
対象企業
NFRDの対象は従業員500人以上の大企業や上場企業、銀行、保険会社などであったため、約1万1,600社にとどまりました。
一方、CSRDは対象企業が約5万社まで拡大されます。
EU域内の大企業(従業員250人以上・売上高4,000万ユーロ以上・総資産2,000万ユーロ以上のいずれか2つを満たす企業)や上場中小企業(純資産残高45万ユーロ・ 純売上高90万ユーロ・従業員数10人の3つのうち、2条件を超えない企業)が対象となります。
EU域外の企業でも、以下の場合はCSRDの対象範囲です。
- EU域内で一定規模以上の売上高がある場合(EU域内売上高が1億5,000万ユーロ超)
- EUにある子会社が「大企業」の基準を満たす場合やEUにある子会社が上場している場合
- EU域内に一定規模以上の子会社や支店を運営する場合(EU支店がEU域内で純売上高4,000万ユーロ超)
しかし、EUは2025年2月26日、開示情報の負担を減らすために「オムニバス法案」を提案しました。とくに中小企業の負担を軽減できるよう、従業員250人以上から1,000人以上に引き上げ、適用対象を大幅に削減しました。
EU域外の企業でも、EU域内売上高(連結ベース)を1億5,000万ユーロ超から4億5,000万ユーロ超に、EU支店がEU域内での純売上高4,000万ユーロ超から5,000万ユーロ超に引き上げられています。
今後もオムニバス法案による変更には、注意が必要です。
開示要求事項
NFRD には明確な開示範囲や開示基準がなかったため、企業によって情報開示の質に差が生じていました。
CSRDでは、ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)の策定により、開示すべき項目が詳細に定められています。
ESRSは、一般的な企業情報に加え、環境、社会、ガバナンスに関する12の基準から構成され、その下に82の開示要件と1,000以上のデータポイントが指定されています。企業間の比較を可能とし、報告の信頼性を高められるように規定されました。
マテリアリティ(重要性)の考え方
NFRDには、特定の定義は言及されていません。しかし、CSRDではダブルマテリアリティ(二重の重要性)の概念を採用しています。
ダブルマテリアリティ(二重の重要性)は、以下の2つの要素から構成されています。
- インパクト・マテリアリティ:企業の活動が社会や環境に与える影響
- 財務マテリアリティ:社会や環境の変化が企業に与える財務的影響
企業がサステナビリティに関連する情報を報告する際、短期・中期・長期にわたって異なる2つの視点から重要性を評価することが必要です。
第三者保証
NFRDでは任意だった第三者保証は、CSRDでは必須となりました。これには、報告された情報の信頼性を確保する目的があります。
ESRSに基づくサステナビリティ報告書は、認定を受けた独立監査機関または認証機関による監査を受けることが義務づけられています。
開示形式
NFRDには、指定された開示形式はありません。しかし、CSRDでは財務情報と非財務情報を単一の電子フォーマット(XHTML)で提出することが定められています。
統一された形式でデジタル化して開示されることにより、投資家や消費者、規制当局などが企業ごとのデータを簡単に比較できるようになりました。
参照:日本貿易振興機構(ジェトロ)|CSRDをめぐる最近の動向
参照:JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)|CSRD 適用対象日系企業のためのESRS 適用実務ガイダンス
適用開始時期
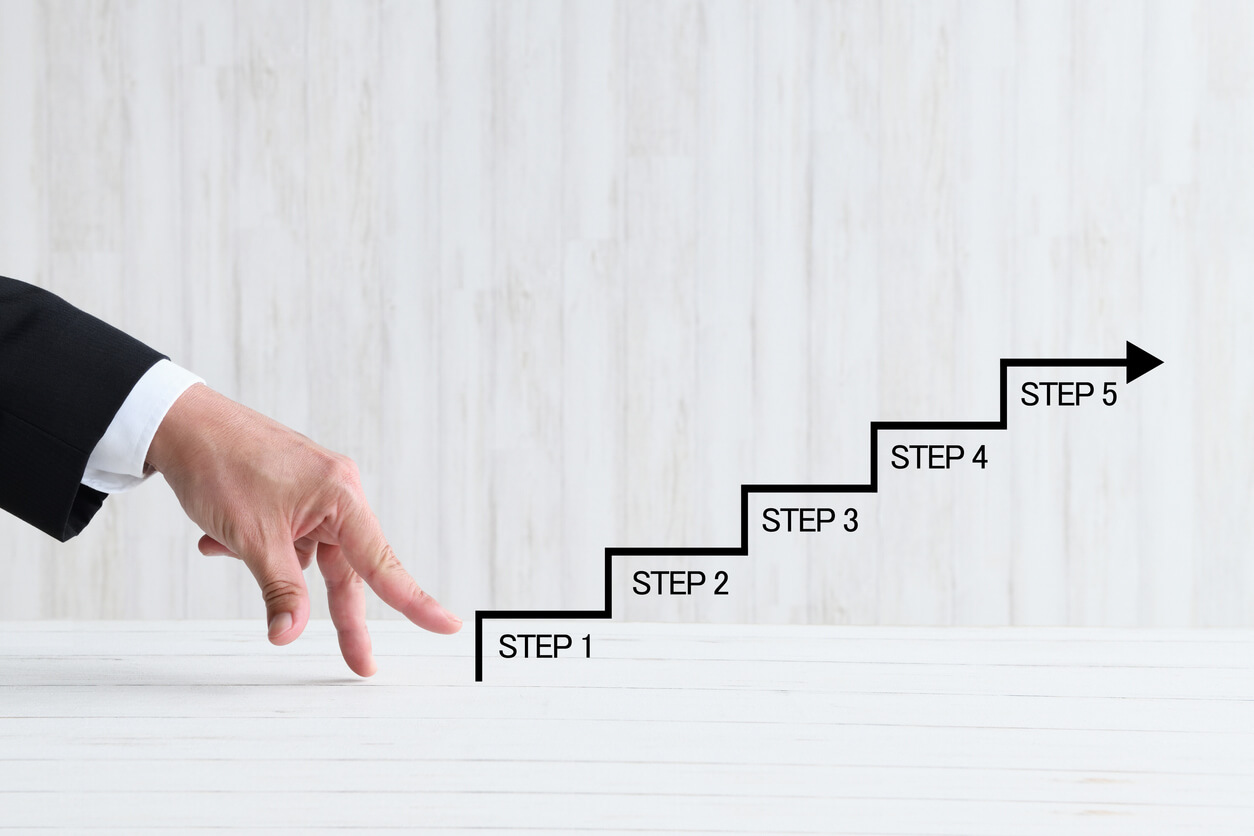
「CSRDの対象ならいつから報告すべきなのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
ここでは、適用開始時期やオムニバス法案による変更点を解説します。
適用開始時期
CSRDは企業の規模や種類によって適用開始時期は異なり、段階的に導入されます。開示内容が多く、データ収集や内部体制の整備に時間がかかるため、4段階に分けられています。
第1波:NFRD対象企業
NFRD(非財務情報開示指令)の対象である従業員500人超の上場企業や銀行などは、2024年会計年度から適用、2025年から報告を行います。
第2波:一定規模以上の大企業
NFRDの対象でなかった上場企業(中小企業を除く)および大企業は、2025年会計年度から適用となり、2026年度から報告が義務づけられます。
EU域内の日系子会社がこの対象の可能性があります。
第3波:上場中小企業
小規模事業者を除くEU域内で上場している中小企業、小規模で複雑でない信用機関、およびキャプティブ保険会社は、2026年会計年度から適用され、2027年から報告を行います。
第4波:EU域外企業
EU域外企業であってもEU域内で一定規模以上の売上高がある場合や、EU域内に一定規模以上の子会社や支店を運営する場合は、2028年会計年度から適用となり、2029年から報告義務が発生します。
該当する日本の親会社を頂点とした企業グループは、2029年3月期から情報開示を始めなければなりません。
オムニバス法案による変更
2025年4月15日にオムニバス法案が採択され、第2波と第3波の適用開始が2年延期になりました。
今後も最新の動向には常にアップデートしておく必要があります。
参照:日本貿易振興機構(ジェトロ)|CSRDをめぐる最近の動向
参照:JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)|CSRD 適用対象日系企業のためのESRS 適用実務ガイダンス
参照:JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)|欧州議会、持続可能性関連規制の適用延期法案を採択、CSDDDは1年延期、CSRDは2年延期へ
参照:金融庁|事務局説明資料
なぜ日本企業にも影響があるのか

ロンドン証券取引所グループの傘下にある金融情報サービス企業・リフィニティブ社のデータによると、CSRDの適用対象となるEU域外企業は1万400社あり、そのうち約8%が日本企業であると報告されました。
CSRDは、EUの新たな指令です。しかし、EU域内の日系子会社や、EUでの売り上げや拠点が一定基準を超えている日本企業は対象で、開示義務が発生します。
CSRDの直接対象外の企業でも、EU域内の取引先や顧客から、サプライチェーンの一員としてESGデータ開示の要請を受ける可能性が考えられます。取引中止のリスクを避けるために早めの準備が必要です。
参照:オルタナ|EU「CSRD/ESRS」、EU域外企業も1万社超が適用対象に
日本企業が今すぐ取るべき対応

CSRD対応は時間がかかるため、対象企業かどうかの確認と並行して、早期に準備を始めることが重要です。
ここでは、日本企業に必要な対応を解説します。
最新の制度概要を理解する
CSRDは「オムニバス法案」により適用時期の延期や開示内容の簡素化が提案されているため、今後も動向には注意しましょう。
常にアンテナをはり、最新情報にアップデートする必要があります。
自社グループへの適用可能性を正確に判断する
自社やグループがEU域内での売り上げや拠点条件を満たしているかを確認します。CSRDが求めるサステナビリティ情報開示の範囲は、自社のみならずバリューチェーン全体に及ぶため、EU域内の取引先や顧客がある場合は注意が必要です。
簡易ギャップ分析
現在の非財務情報開示やESG対応状況と、CSRDで求められる項目とのギャップを洗い出すことが重要です。
とくに、企業の活動が社会や環境に与える影響と、社会や環境の変化が企業に与える財務的影響にはどのようなものがあるのか、ダブルマテリアリティ評価を実践する必要があります。
温室効果ガス排出量や人権、労働環境などのデータ収集体制を整備し、必要に応じてシステムを活用することが重要です。
第三者保証への対応
CSRDは開示情報に対する第三者保証を義務づけられていますが、日本の開示規則ではまだ必須ではありません。
多くの日本企業にとって非財務情報に係る内部統制の強化が課題となります。第三者保証(監査)に耐えられるよう、データの正確性と証拠の保存方法などを確立することが重要です。
対応ロードマップを共有
CSRDは開示項目が多く、データ収集・社内体制整備・第三者保証対応など、複数部門にまたがる作業が発生します。期限内に間に合うよう、適用開始時期から逆算して「いつ・誰が・何をするか」を整理した行動計画が必要です。
経営層や各部門と連携して対応ロードマップを共有することで、社内全体が同じ方向を向いて効率的に対応でき、初年度からスムーズなCSRD報告が可能になります。
参照:JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)|CSRD 適用対象日系企業のためのESRS適用実務ガイダンス
CSRD対応はEUだけでなく日本企業も関係あり

CSRD(企業サステナビリティ報告指令)は「EU企業の話」ではなく、日本企業にとっても避けられないテーマです。早期に準備を進めることで、国際基準に適合したデータの仕組みを整備でき、将来的な事業拡大や投資家からの評価向上が期待できます。
最後に、CSRDを理解するための5つのポイントを確認しておきましょう。
- 目的:CSRDは、企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する情報を透明かつ比較可能にするためのEUの新ルールである
- 対象範囲:EU域内の大企業や上場企業だけでなく、一定条件を満たす日本企業にも適用される
- 報告基準:欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に沿って開示し、環境・社会への影響と財務への影響の両面を評価する必要がある
- スケジュール:2024年度から段階的に適用開始される
- 影響と対応:取引先からの情報提供要請や第三者保証対応が必要となるため、早期にデータ収集体制や内部統制を整えることが重要である
対応は義務ですが、国際市場で競争力を強化する最大のチャンスです。CSRD対応を未来への投資にしましょう。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











