マテリアリティとSDGsの関係を解説!企業事例から学ぶ特定プロセス

「マテリアリティの定義がよく分からない」「自社でどう取り入れるべきか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。マテリアリティは、企業が信頼を得て持続的に成長するために欠かせない考え方です。
本記事では、マテリアリティの基本やSDGsとの関係、特定プロセス、そしてニチレイや富士通などの企業事例を解説します。この記事を読めば、マテリアリティを特定する際に必要な実践的な視点を得られます。
マテリアリティとは

マテリアリティとは、企業が長期的に成長していく上で、優先的に重要となる課題を指します。日本語では「重要課題」とも呼ばれ、企業がどのテーマに力を入れるべきかを明確にする考え方です。
従来のマテリアリティは、財務に関する課題を重要視していました。収益性、資産・負債、キャッシュフローなどを含む財務パフォーマンスにどのような影響があるかが、投資家などが意思決定する際の主な基準でした。
その後、企業の社会的責任が広まり、マテリアリティの概念も環境や社会への影響など、非財務的側面を重要視するようになります。企業は自社活動が社会や環境に与える影響を評価し、報告することが求められるようになりました。
さらに近年、とくに環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する報告の重要性が高まる中で「ダブルマテリアリティ」という新たな概念が登場しました。
これは、環境や社会などの外部要因が企業の財務的価値や事業に与える影響(財務的マテリアリティ)と、企業活動が社会や環境に及ぼす影響(インパクト・マテリアリティ)の両方を考慮するものです。EUの企業のサステナビリティ報告指令(CSRD)は、この考え方を支持しています。
マテリアリティは、時代のニーズや規制の変化に応じて進化を続けています。
参照:LinkedIn|From GRI to ISSB: The Evolution of Materiality in Global ESG Standards
参照:日経ESG|ダブルマテリアリティを巡る議論からの見えてくる課題
マテリアリティの重要性とメリット

マテリアリティが重要な理由は、企業の評価が売上や利益といった数値だけでなく、環境への配慮や社会的責任などにも直結するためです。ここでは、マテリアリティが企業に与えるメリットを解説します。
持続可能な経営の基盤
マテリアリティは、企業がどの課題に優先的に取り組むべきかを示す指標です。
「事業を通して医療支援にどのように貢献するか」「デジタル技術で食料課題をどのように解決するか」など、企業がサステナビリティへの取り組みを明確にすることで、経営の方向性が固まり、信頼性の高い戦略を打ち出せるようになります。
マテリアリティは企業の信頼性や競争力を高め、持続可能な成長につながる基盤となります。
社会的評価の向上
社会的評価で重要視すべき点は、売上や利益といった財務情報から、「環境に配慮しているか」「人権を守っているか」などの非財務情報へ移り変わっています。
企業は、自社の資源や強みをサステナビリティと結びつけた指標を打ち出すことで、投資家には「将来性のある成長戦略」、顧客には「安心して商品やサービスを選べる企業姿勢」、従業員には「働く意義のある環境」といった魅力をアピールできます。
企業が社会の持続可能性への参加・貢献姿勢を示すことは、社会からの信頼と共感を得る有効な戦略です。
ESG投資の促進
地球規模で気候変動問題や人権問題などの社会課題が深刻化する中、注目されているのがESG投資です。世界のESG投資残高は右肩上がりで、2014年度では18.3兆ドルでしたが、2022年には30.3兆ドルまで増加しました。
企業がマテリアリティを特定して開示することで、投資家から高い評価を受け、持続可能なESG投資が期待できます。
リスク管理と事業機会の創出
マテリアリティを特定することは、企業が直面するリスクを早期発見し、適切な対応策を講じるために欠かせません。
以下の例は、企業活動に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
- 原料調達の生産地や工場での強制労働や児童労働といった人権侵害
- 工場からの排出による環境破壊
- 気候変動による自然災害の増加
これらを事前に認識し、改善策を実行することが、安定した長期的な事業に直結します。さらに、課題への対応はリスクを減らすだけでなく、新事業の可能性を開く機会にもなります。
たとえば、原料を調達する発展途上国の労働者への経済的支援につながるサステナブルなサービスは、消費者からの支持を得てブランド力を高めることにもつながるでしょう。また、カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギーの導入は、コスト削減だけでなく新たな市場参入の機会を創出します。
マテリアリティの特定は、企業にとって「リスク管理」と「新事業の機会」の両面で欠かせない取り組みです。
参照:経済産業省|「社会の持続可能性の向上と長期的な企業価値の創出に向けたESG情報開示のあり方」に関する調査研究報告書
マテリアリティとSDGsの関係

SDGsとは、国連が発表した持続可能な開発目標のことで、17の目標と169のターゲットから成り立っています。
経済産業省の「SDGs経営ガイド」にも示唆されているように、1つの企業が、17の目標すべてに貢献しようとすることは困難ですが、1つのマテリアリティを通して複数の目標に取り組むことは可能です。
たとえば、キヤノンは、社会分野において「人権と労働」を最重要マテリアリティに位置づけています。アジアの生産拠点を中心に労働時間の管理を徹底したり、児童労働者の有無を確認したりするなど、労働・安全衛生のリスク回避に取り組んできました。これらの活動は、以下のSDGsの目標に貢献すると考えられます。
- SDGs5「ジェンダー平等を実現しよう」
- SDGs8「働きがいも経済成長も」
- SDGs10「人や国の不平等をなくそう」
- SDGs16「平和と安全をすべての人に」
企業は、SDGsを意識したマテリアリティを設定し、それを実際の行動計画へと落とし込むことが重要です。
参照:外務省|グローバル指標(SDG indicators)
参照:キヤノングローバル|環境・社会分野における重点課題(マテリアリティ)
マテリアリティの特定プロセスと企業事例
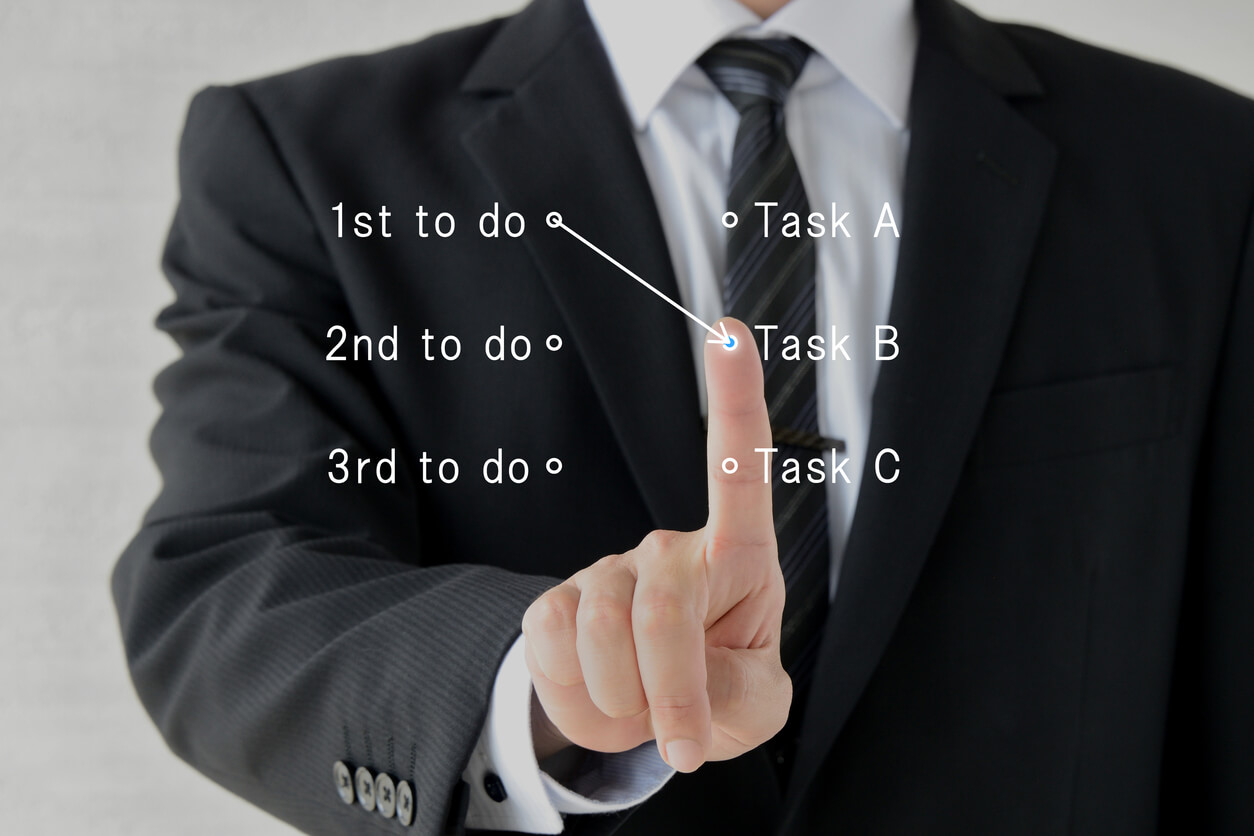
自社のマテリアリティを特定し、その内容を開示するプロセスは、透明性や信頼性を高める上で、持続可能な経営に不可欠です。ここでは、マテリアリティの特定プロセスを企業事例とともに解説します。
課題リストアップと整理
まず、自社に関連する環境・社会課題を幅広く洗い出すことが重要です。
その際、SDGsなどの国際的なガイドラインを参考にしながら、気候変動、資源循環、人権、労働環境、地域社会との関係など、自社の事業に関連するテーマを一覧化します。
課題のリストアップは、原材料の調達から製造、販売、使用、廃棄に至るまでを視野に入れて検討することが不可欠です。
たとえば、電気機器メーカーの場合、生産時よりも製品の使用時に多くのエネルギーが消費されます。そのため、工場での排出量よりも製品使用時の温室効果ガス排出をマテリアリティとして重視し、報告する必要性が高まっています。
課題の評価
リストアップされた課題について、それぞれの重要性を評価します。評価基準としてよく用いられるのは、次の2軸です。
- 社会やステークホルダーに対する影響度:投資家、株主、取引先、消費者、従業員などの関心度や意思決定への影響
- 自社グループに対する影響度:事業におけるリスクと機会、企業価値への影響
「企業にとってどれほど重要か」「社会からどれだけ程度注目されているか」をもとに優先順位を設定し、最も重視すべき課題を絞り込みます。
実際にニチレイでは、マテリアリティは成長戦略に直結すると捉えた上で、事業成長を実現する課題を「攻め」、企業価値の毀損を防ぐ課題を「守り」と位置づけ、この2軸で自社のマテリアリティを評価しています。その結果、以下の5つのマテリアリティを特定しました。
- 食と健康における新たな価値の創造
- 食品加工・生産技術力の強化と低温物流サービスの高度化
- 持続可能な食の調達と循環型社会の実現
- 気候変動への取り組み
- 多様な人財の確保と育成
また、評価に際しては、経営層や事業部門、若手社員や海外社員、社外取締役などの意見に加え、取引先や有識者、NGOを含む社内外からのアンケートを通じて、リアルな声を収集し、マテリアリティの特定に反映させることが推奨されています。
マテリアリティの特定
分析結果をもとに、優先度の高い課題を特定します。社会や投資家、取引先、消費者などへの影響度が高く、自社事業にも大きな影響を与える課題がマテリアリティとして適切です。
実際には、経営基盤に関わる課題と、価値創造や企業成長につながる課題の2つのカテゴリーに分けて議論する企業もあります。
富士通グループは「必要不可欠な貢献分野」(事業活動)と「持続的な発展を可能にする土台」(資本・基盤)の2つに分けて整理した上でマテリアリティを特定しました。
- 必要不可欠な貢献分野(地球環境問題の解決・デジタル社会の発展・人々のウェルビーイングの向上)
- 持続的な発展を可能にする土台(テクノロジー・経営基盤・人材)
判断結果の妥当性確認と承認
マテリアリティは特定しただけで終わりではなく、社会的責任が適切に果たされるよう、組織として実施しなければいけません。
優先度の高い課題を抽出した後は、サステナビリティ推進委員会や経営会議、取締役会など、経営レベルの承認が不可欠です。経営層の承認を得ることで、マテリアリティを経営戦略の一部として位置づけられます。
ANAホールディングスでは、経営企画部門を中心にプロジェクトを組み、社外有識者の意見や経営層による確認を経て、マテリアリティを策定しています。
継続的な見直し
社会や経営環境の変化に伴い、重要課題の内容も変わるため、マテリアリティは定期的に見直す必要があります。
コンサルティング&エンジニアリンググループであるID&Eホールディングスは、5つのマテリアリティを特定し、「IDEALな世界の実現に向けて」を全体のテーマに設定しました。さらなるマテリアリティの推進にあたり、社内外の環境変化を踏まえ、継続的に目標値の見直しやマテリアリティの見直しを実施しています。
参照:富士通|マテリアリティ
参照:ID&Eホールディングス|マテリアリティ -IDEALな世界の実現に向けて-
マテリアリティで企業価値の向上を

マテリアリティは、企業が長期的に成長するために優先すべき重要課題であり、社会的信頼を得るために欠かせません。時代の変化とともに、財務面のみならず非財務面へと対象が広がり、ダブルマテリアリティの視点が求められる今、SDGsとの連動や国際基準に基づく透明性の高い開示が必要とされています。
企業事例からも分かるように、マテリアリティは経営戦略と社会課題の両面の観点から検討することが求められています。自社の資源や強みを活かしたマテリアリティの特定が、持続可能な経営を支える基盤となり、今後ますます企業価値を高める鍵となるでしょう。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











