トレーサビリティ食品とは?仕組みと食の安全のために、私たちが知っておくべきこと

私たちが毎日口にする食品は、どこでどのように作られ、どのように運ばれてきたのでしょうか。そんな疑問や不安に応える仕組みが「食品トレーサビリティ」です。生産から加工、輸送、販売までの情報を追跡できるように整備することで、仮に何か問題が起きても原因を早期に発見できます。このような仕組みは、消費者に食の安全と安心を提供するとともに、購入行動にもつながるはずです。
本記事では、食品トレーサビリティの概要や必要性、そして消費者にとってのメリットをわかりやすく解説します。
食品トレーサビリティの概要

食品トレーサビリティとは、食品の生産、加工、輸送、販売といった各段階における情報を記録し、保存することです。食品が消費者に届くまでどのような移動ルートをたどったかを「トレースフォワード(追跡)」や、「トレースバック(遡及)」によって把握できる状態でなくてはなりません。
このようなトレーサビリティを導入することで、万が一何らかの問題が発生した場合でも、迅速に追跡や原因究明、製品の回収が行えるようになります。また、トレーサビリティは生産者だけでなく、消費者にとっても食品が「いつ・どこで・どのように」生産されたのかがわかる仕組みとなります。
食品トレーサビリティは、問題が起きた際に原因の特定や対象製品の迅速かつ正確な回収を可能にするだけでなく、消費者の安全・安心にも貢献するでしょう。
関連記事:SDGsにも関連するトレーサビリティとは?意味やシステムを簡単に解説
参考:GENBA KAIZEN Lab「食品トレーサビリティとは?メリットやデメリット、事例も解説」
トレースフォワードとトレースバック
トレースフォワード(追跡)は、製品がどのようなルートをたどり消費者に届いたかを順を追って確認することです。問題が発生した場合には、その製品がどの店舗や消費者へ出荷されたかを特定できるため、速やかな回収・情報開示に役立ちます。
一方、トレースバック(遡及)は、製品がどこから来たかをさかのぼって追跡することです。問題が発生した製品の原材料や製造工程の供給元を特定し、原因究明や再発防止策を講じるために活用されます。
この2つの仕組みは、食品の安全確保に不可欠であり、消費者の信頼を守るためにも欠かせません。
チェーントレーサビリティと内部トレーサビリティ
チェーントレーサビリティは、食品の原材料調達から製造、流通、販売、消費に至るまで、サプライチェーン全体における食品の移動履歴を追跡できる仕組みです。
一方、内部トレーサビリティは、サプライチェーン全体ではなく、特定の工場や企業の内部に限定して、原材料の受け入れから製造、出荷までの過程を追跡する仕組みです。
これらの2つの仕組みを連携させることで、食品の安全性と品質管理が強化されています。
参考:食品IT NAVI「食品のトレーサビリティ(トレサビ)とは?取り組みでの課題や対応事例を紹介」
参考:SHARP 「トレーサビリティとは?仕組みやメリットを詳しく解説」
トレーサビリティはなぜ必要か

トレーサビリティが必要とされるようになったきっかけは、2000年頃に相次いだ食品に関する事件や事故が挙げられます。
海外ではBSE(牛海綿状脳症)問題が社会的に大きな影響を及ぼしました。海外でBSEに感染した牛が日本に輸入された際、国民の間では牛肉や関連製品への強い不安が高まりました。これを払拭するために、日本では2003年に「牛肉トレーサビリティ法」が成立し、すべての牛や牛肉に個体識別番号を付けるよう義務付けられたのです。牛が生まれてから食肉として処理されるまで、どのような経路をたどって運ばれてきたのかを追跡できる仕組みが整備されました。
トレーサビリティは、牛肉だけでなく米にも義務付けられています。2008年には、カビ毒に感染した米が食用として日本に輸入された事件があり、その後、米の産地や品種なども記録・保存されるようになりました。
参考:食品IT NAVI「食品のトレーサビリティ~導入の背景・目的、法令、取組みの基本、最近の調査結果~」
食品トレーサビリティの実施方法
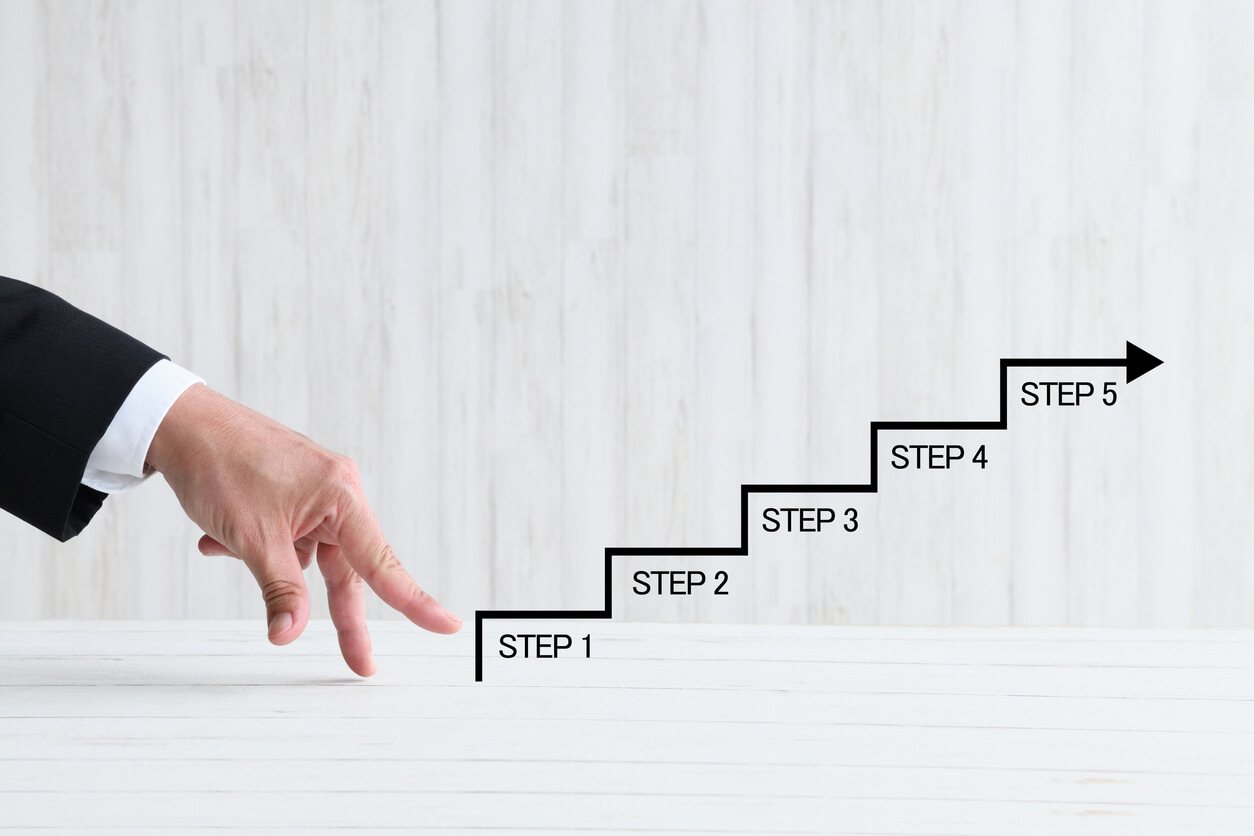
食品トレーサビリティは、消費者に安全・安心を届けるだけでなく、企業やサプライチェーンにとっても問題発生時に速やかな対応を可能にします。
ここでは、食品トレーサビリティの実施方法について解説します。
ステップ1:入荷先・出荷先の記録
まず、食品の入荷・出荷時には、以下の基本情報を漏れなく記録します。
- いつ(入荷日・出荷日)
- どこから(入荷先)、どこへ(出荷先)
- 何を(品名)
- どれだけ(数量)
これらの情報は、通常送り状や納品書に記載されているため、比較的簡単に取得できます。まずは、紙やエクセルなどに記録しておくだけでもよいので、正しく記録・保存することで、万が一問題発生時にも流通経路の特定がしやすくなります。
参考:飲食業界イノベーションWeek 「食品トレーサビリティの取り組みと導入メリットとは?課題点や事例を紹介」
参考:GENBA KAIZEN Lab「食品トレーサビリティとは?メリットやデメリット、事例も解説」
ステップ2:食品の識別
続いて、食品を識別するためにロット管理を行います。ロット管理とは、同じ条件で製造・加工された食品や原材料を「ロット」としてまとめ、識別番号を付けて管理する仕組みです。例えば、同じ日に作られた製品を1つのロットとみなし、製造日や製造ラインを番号に含めるのが一般的です。
このロット管理により、万が一事故などが発生した場合に問題となるロットが特定でき、どこまで回収が必要か明確になります。また、賞味期限の管理や先入れ先出しの徹底にも役立ち、食品の安全性・品質保持に欠かせない重要なステップとなります。
参考:キャムマックス「食品の在庫管理で失敗しない「ロット管理」方法をご紹介」
参考:IPROS「【専門知識解説】『ロット』とは?効果的な管理方法5選を紹介!」
ステップ3:識別した食品の対応づけ
最後に、以下の情報を対応づけ(紐付け)し、記録・管理します。
- 入荷した原材料のロットと入荷先
- 入荷ロットと製造ロット
- 製造ロットと出荷先の情報
対応づけを行うと、事故が発生した際にもロットや影響範囲が特定でき、速やかな回収が可能となります。これは、安全性の確保だけでなく、消費者や関係者へ正確な情報を提供するうえでも大事なステップです。近年では、ITシステムを活用して業務の効率化を図る企業も増えつつあります。
参考:飲食業界イノベーションWeek 「食品トレーサビリティの取り組みと導入メリットとは?課題点や事例を紹介」
参考:NECソリューションイノベータ「トレーサビリティとは?食品×ITの可能性」
食品トレーサビリティを導入するメリット

食品トレーサビリティの導入は、ハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし、導入によってさまざまなメリットが得られます。
ここでは、導入した際のメリットを紹介します。
問題発生時の対応力向上
何か問題が発生した場合、トレーサビリティによって製造履歴や流通経路が記録されているため、「いつ」「どこで」「どの原材料」「どの工程」で問題が起きたのかを速やかに特定できます。これにより、該当のロットが正しく把握でき、必要最小限の範囲で製品回収(リコール)が可能です。
迅速かつ正確なリコール対応は、消費者の健康への被害を防止するだけでなく、企業の信頼性やブランドイメージにも直結します。また、過剰な回収によるコストや食品ロスの削減にもつながり、リスク管理にも貢献します。
参考:Mottoクラウドカメラ「食品トレーサビリティシステム導入の手引き|メリットや課題も解説」
参考:飲食業界イノベーションWeek 「食品トレーサビリティの取り組みと導入メリットとは?課題点や事例を紹介」
参考:NiGK Corporation「食品トレーサビリティとは?メリットや課題などを簡単に紹介」
フードロス削減
トレーサビリティの導入により、食品の生産から流通、消費までの流れや賞味期限などの情報をリアルタイムで把握できるようになります。これにより、過剰在庫や滞留を防いだり、消費期限が近い製品を特定したりできるため、販売促進や値下げなどの対策がとりやすくなります。結果として、フードロス削減にもつながるでしょう。
参考:飲食業界イノベーションWeek 「食品トレーサビリティの取り組みと導入メリットとは?課題点や事例を紹介」
参考:GENBA KAIZEN Lab「食品トレーサビリティとは?メリットやデメリット、事例も解説」
企業イメージと消費者満足度の向上
トレーサビリティによって製造履歴や流通経路が明確になるため、消費者は安心して商品を購入できます。また、透明性が高まることで、食品の安全に対する取り組みや品質向上、さらに従業員の意識改革にもつながります。
これにより、企業への信頼が高まり、イメージアップや消費者満足度の向上にも寄与するでしょう。
参考:zaico 「トレーサビリティとは?トレーサビリティとはを簡単にわかりやすく解説」
食品トレーサビリティのデメリット

食品トレーサビリティには、食の安全を確保するうえで多くのメリットがありますが、その一方でデメリットも存在します。ここでは、そのデメリットを紹介します。
システムの導入にコストがかかる
食品トレーサビリティを導入する際には、初期費用がかかります。
- システム開発費用
- 専用ハードウェア(バーコードスキャナー、プリンター、サーバーなど)の購入費用
- インフラ整備費用
- コンサルティング費用
- 従業員の研修費用
さらに、導入後も保守やメンテナンス費用やライセンス料、データ管理や更新にかかる人件費など、さまざまな維持コストが発生します。
特に中小企業にとっては、初期導入コストや運用コストが大きな負担となり、資金調達やIT人材不足が課題となるケースが少なくありません。
また、複数の取引先とデータを連携する際にはシステム間の調整も必要なため、追加コストが発生する場合もあります。
参考:NiGK Corporation「食品トレーサビリティとは?メリットや課題などを簡単に紹介」
参考:Mottoクラウドカメラ「食品トレーサビリティシステム導入の手引き|メリットや課題も解説」
データ改ざんリスクの恐れ
食品トレーサビリティでは、製造履歴や流通経路をシステム管理することが多いため、このデータの正確性と信頼性が非常に重要です。しかし、システムのセキュリティが不十分な場合や、アクセス権限の管理が不十分な場合には、内部で意図的にデータが改ざんされるリスクも否定できません。
リスクを低減するためには、システムの暗号化や厳格なアクセス権の管理、更新履歴の記録などのルール化が必須です。
ただし、近年は改ざん防止のためにブロックチェーン技術も注目されており、改ざんが難しい技術を提供する企業も増えつつあります。
*ブロックチェーン:仮想通貨の取引技術として考案された、暗号化技術を用いてネットワーク上の複数のコンピュータ間でデータを同期・記録する方法。データを分散管理できる。
参考:飲食業界イノベーションWeek 「食品トレーサビリティの取り組みと導入メリットとは?課題点や事例を紹介」
参考:食品IT NAVI「食品のトレーサビリティ(トレサビ)とは?取り組みでの課題や対応事例を紹介」
参考:NECソリューションイノベータ「トレーサビリティとは?食品×ITの可能性」
参考:キーエンス「トレーサビリティにおけるブロックチェーンとは」
サプライチェーン全体での協力体制が不可欠
食品は生産者や流通業者、小売業者など多くの経路をたどって消費者のもとに届けられるため、各課程で正しい情報を記録・共有することが必要です。
しかし、関係者間で使用しているシステムや管理方法が異なる場合、情報の連携がスムーズに行えないことも少なくありません。このような状況ではトレーサビリティが十分に機能しないことがあります。
そのため、サプライチェーン全体で統一されたプラットフォームやシステムを導入し、共通のルールや認識を持つことが重要です。
参考:飲食業界イノベーションWeek 「食品トレーサビリティの取り組みと導入メリットとは?課題点や事例を紹介」
参考:NiGK Corporation「食品トレーサビリティとは?メリットや課題などを簡単に紹介」
食品トレーサビリティで食の安全が守られる

食品トレーサビリティは、食の安全・安心を守るために欠かせない仕組みです。BSEや米の不正輸出などの事件をきっかけに法整備が進み、今では入出荷記録やロット管理を通じて、問題発生時の速やかな対応やフードロス削減にも貢献しています。
一方で、システムの導入にはコストやデータ改ざんリスク、サプライチェーン全体での協力体制などの課題も残されています。透明性を高めて消費者の信頼を築くためには、企業と社会が一体となった取り組みが不可欠です。
多くの企業が食品トレーサビリティを導入し、消費者の安全確保を目的として積極的な情報開示に取り組んでいます。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











