SDGs11の目標とは?10のターゲット、世界と日本の現状を解説

SDGs11の目標は「住み続けられるまちづくり」をテーマにしていることは分かるが、課題や取り組み事例が具体的にイメージできないと感じている方もいるかもしれません。
本記事はSDGs11の目標が掲げるターゲット、世界や日本の現状、解決のヒントを解説します。企業・自治体・個人の取り組み事例もまとめました。読めば、目標達成のために明日から何をすべきか行動が明確になります。
SDGs11の目標とは?

SDGs11の目標は、「住み続けられるまちづくりを」をテーマとした目標です。誰もが安全で安心、そして持続可能な暮らしを送れる社会を目指しています。
現在、世界では都市化が問題視されています。1990年以降、世界全体の都市化が進み、2007年には都市に住む人口が全体の半分を超えました。2050年には人類全体の3分の2に当たる60億人以上が都市で生活することが予測されています。
都市の発展は生活に便利さをもたらす一方で、スラムの拡大や住宅不足、交通渋滞、大気汚染などの課題を生み出します。持続可能なまちづくりを実現させるためには、都市化への対策が重要です。
参照:国土交通省|世界で進行する都市化の傾向と都市開発戦略(その1)
SDGs11の目標が掲げるターゲットを解説

SDGs11の目標「住み続けられるまちづくりを」には、具体的な行動の指針となる10のターゲット(11.1〜11.c)が定められています。これらは都市や地域が直面する課題に対して、「2030年までに何を改善すべきか」を明確に示したものです。
SDGs11の目標が掲げるターゲットの構成
SDGs11の目標で定められたターゲットは、大きく分けると行動目標と実施手段の2つの項目から構成されています。
11.1から11.7は具体的な数値目標または行動目標です。住居・インフラ・交通・都市計画・文化や環境の保全・防災・公共空間など、2030年までに実現すべき結果・状態を明記しています。
11.aから11.cは具体的な実施手段です。目標を達成するために必要な政策、計画、連携、国際的な支援といった具体的な方法が示されています。
SDGs11の目標が掲げるターゲット
SDGs11の目標が関係する分野は、スラムや空き家問題・交通・文化遺産や自然遺産の保全・防災・大気やごみなどの環境問題・都市計画など、多岐にわたります。
11.1 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。
11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。
11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。
11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。
11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。
11.6 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。
11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。
11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。
11.b 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。
11.c 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。
SDGs11の目標が示すターゲットは、都市や地域が直面する課題を解決し、各国や自治体、企業が計画を立てやすくするための道しるべになっています。
参照:外務省|我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ(p22)
世界の現状と課題

SDGs11の目標「住み続けられるまちづくり」は、都市の持続可能性を高めるために必要な目標です。ここでは、目標11が抱える世界の現状と課題を解説します。
人口集中とスラム化
世界の都市部に人口が集中することで、懸念される問題の一つがスラムの問題です。スラムとは、都市部の一角に存在する貧困者が集中して生活する地域を指します。住宅環境、基本的なインフラなどが整備されておらず、衛生面や安全面が懸念されています。
世界全体のスラム住民は、8億3,300万人にのぼり、その数は発展途上国を中心に増え続けているのが現状です。スラム化の問題を放置すれば、社会不安や犯罪増加などの治安の悪化をもたらし、やがてあらゆる市民に影響を与えます。
大気汚染・温室効果ガスの排出
世界の都市では経済活動や交通が集中するため、大気汚染と温室効果ガスの排出が深刻な課題です。
都市は面積にして地球の陸地部分のわずか3%にすぎないにもかかわらず、エネルギー消費は60〜80%、温室効果ガスの排出量は75%を占めています。
温室効果ガス排出がもたらす気候変動は、私たちの時代における最大の課題の一つです。自転車や公共交通の利用促進などが持続可能なまちづくりに求められています。
2016年時点で、都市の住民の90%は安全でない空気を吸っているという報告もあります。大気汚染は、健康被害を引き起こすため、早急に解決が必要です。
自然災害と復興の困難さ
自然災害による復興の難しさも重要な課題です。気候変動の影響で洪水や台風、熱波などが増え、多くの人々の生活を脅かしています。
2023年には、自然災害の影響を受けて、2,640万人が避難や移住を余儀なくされました。自然災害に対する備えや復旧体制の強化が求められています。
参照:国連広報センター|目標 11 都市を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
参照:国連広報センター|住み続けられるまちづくりはなぜ大切か
日本の現状と課題
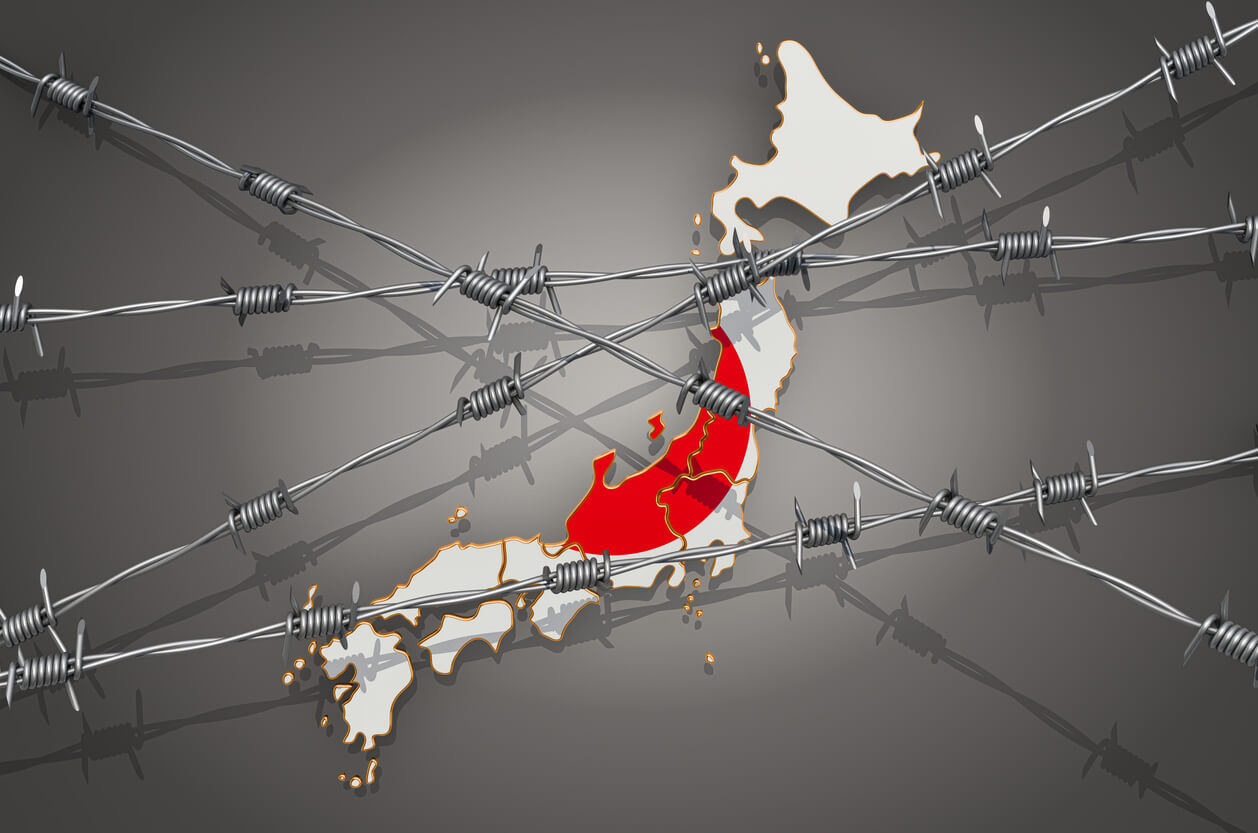
日本で深刻化している少子高齢化は、SDGs11の目標に大きな影響を与えています。続いては、日本の現状と課題を解説します。
都市一極集中と地方の過疎化
日本では、都市への人口集中と地方の過疎化が大きな課題の一つです。
2018年には東京圏の住民の人口が、日本の人口の29%を占める約3,700万人にのぼったことが報告されました。若い世代が進学や就職で都市部へ移動し、地方には高齢者が残る傾向が強まっています。
都市部では住宅価格の高騰や交通渋滞が深刻化し、地方では人口減少による公共交通の衰退や公共サービスの維持が難しくなっています。「住み続けられるまち」を考えるうえで、都市と地方のバランスをどう取るかが重要なテーマといえるでしょう。
高齢化と買い物難民
日本は世界で最も高い高齢化率が報告されています。2025年における65歳以上人口は総人口の29.4%を占め、過去最高を記録しました。
高齢になるほど自分で運転することが困難になるため、買い物の移動に不便さを感じる買い物難民が増加していることが問題視されています。
農林水産省のデータによると、2020年における食料品を購入することが困難な人口は、全国で904万人と推計され、このうち75歳以上の占める割合は63%と報告されました。
高齢者を中心に、誰もが買い物や通院を気軽にできるような移動販売車や宅配サービスなど、環境整備が重要です。
空き家問題
高齢化が進むにつれて深刻化しているのが、空き家の問題です。2023年の空き家は900万2,000戸で、総住宅数に占める空き家の割合が13.8%と過去最高を記録しました。
空き家の増加は、倒壊や火災の被害、犯罪誘発、衛生の悪化や悪臭の発生、景観悪化などの住民にもさまざまな影響があると懸念されています。
空き家の問題を解決するためには、管理不全の空き家を取り壊したり、人が集まりやすい施設に空き家を再利用したりするなど、地方が活性化するような対策が必要です。
災害大国・レジリエンスの必要性
日本は地震や台風、豪雨などの自然災害が多い災害大国です。自然災害による被害が出れば、経済や生活へ大きな影響を与えます。災害が発生しても迅速に復旧できる「レジリエンス(回復力)」のある社会づくりが重要です。
近年、国内では豪雨災害が頻発化し、道路や鉄道の寸断など、各地で甚大な被害が発生しています。2019年の水害被害額は、全国で約2兆1,800億円となり、1年間の津波以外の水害被害額が統計開始以来最大となりました。
防災・減災に向けた備えを強化し、災害に強いまちづくりを進めることが、日本にとって急務といえます。
参照:総務省統計局|統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-
参照:農林水産省|2020年食料品アクセス困難人口の推計結果の公表及び説明会の開催について
参照:総務省|令和5年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果
参照:国土交通省|令和3年版国土交通白書ダイジェスト版「危機を乗り越え豊かな未来へ」
企業の取り組み事例

企業が実際に行っている、持続可能なまちづくりを紹介します。移動販売や地域連携、スマートタウン、災害時の支援など、自社の強みを生かした事例をまとめました。
Panasonic「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)」
Fujisawa SSTとは、神奈川県藤沢市にあるパナソニックの工場跡地に開発された、100年先の未来を見据えたサスティナブルな街です。1990年比で二酸化炭素の排出量の70%削減を掲げ、達成を実現しました。
「生きるエネルギーがうまれる街。」をコンセプトに掲げ、東京ドーム4個分に相当する土地に、1,000世帯の住宅、商業・福祉・教育施設などが建設されました。
すべての戸建住宅に太陽光発電システムと蓄電池を備え、エネルギーの自産自消を推進しています。エネルギーを効率的に管理することにより、災害時にもライフラインを確保できる体制が整うようになりました。
参照:Fujisawa SST
参照:Panasonic|Panasonicのスマートシティ事業
参照:Panasonic Group|10周年を迎えたFujisawaサスティナブル・スマートタウンが完成「生きるエネルギーがうまれる街。」第2章、はじまる
参照:Panasonic Group|まち全体でより良いくらしを提供する「サスティナブル・スマートタウン」
移動スーパーとくし丸
とくし丸は、買い物が困難な人の家の近くまで出向き、生鮮品をふくむ日用品をその場で選んで買えるようにする移動スーパーです。冷蔵設備つきの軽トラックを活用することで買い物の楽しさと、地域の見守りを同時に実現し、生活インフラの強化を実現しました。
「売りすぎない」方針で、買いすぎや食品ロスの防止にも努めています。スタッフがその場で会話しながら好みや体調を聞き、次回のリクエストにも対応しています。移動スーパーの提供は、高齢者を中心とする生活インフラを強化した成功事例といえるでしょう。
参照:移動スーパーとくし丸
JAPAN AIRLINES「復興支援」
JALは、災害発生時に臨時便を設定し、救援物資の輸送を行うなど、被災地への迅速な支援を実施しています。
これまでに、被災者支援マイルの寄付受付、特別旅行商品の提供などを継続的に実施し、移動の確保と地域の復興に大きく貢献しました。
また、経済的困難を抱えた被災地の子供たちの応援にも力を入れています。被災地では多くの子供たちが将来の夢をかなえるために進学できるように、塾や習い事で利用できる「スタディクーポン」を給付しています。
参照:JAPAN AIRLINES|JAL北陸復興応援クーポン
参照:JAPAN AIRLINES|被災地の子どもたちの応援・被災された方々の心に寄り添う
海外の事例について、さらに知りたい方は下記の記事がおすすめです。
関連記事:SDGs11「住み続けられるまちづくりを」の日本・海外の取り組み事例を課題とともに紹介
自治体の取り組み事例

自治体は、暮らしの安全・移動の便利さ・環境負荷の軽減を束ねる中核です。ここでは、自治体がそれぞれの課題や教訓をもとに実施している事例を紹介します。
富山市
富山市では、公共交通の衰退や中心市街地の空洞化など、都市課題を解決するため、「コンパクトなまちづくり」に約15年以上取り組んでいます。
公共交通の活性化を目指し、LRT(次世代型路面電車システム)を導入しました。利便性・快適性の向上を図るために、開業した富山ライトレールの駅に路線バスを接続させました。移動しやすくなったことで、開業前と比較して、公共交通の利用者数が平日で約2.1倍、休日で約3.4倍へと大幅に増加し、高齢者の利用も増えています。
外出しやすい環境づくりに尽力したことで、車に依存したライフスタイルを改善し、歩いて暮らせるまちづくりを実現しました。
神戸市
神戸市は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、防災・レジリエンスの強化に努めています。
神戸市情報マップやLINE公式アカウントを通じて、災害時の避難情報やその他の重要な情報を市民が簡単に閲覧できる環境を整備しました。
さらに、デジタルツイン技術を用いて、災害時の避難シミュレーションを行っています。デジタルツイン技術とは、現実世界を再現したコンピュータの中で避難訓練を行う技術のことです。災害時の避難を可視化することで、一般市民が安全な避難状況を視覚的に理解できるようにしています。
参照:理化学研究所|神戸市の防災計画にデジタルツインを生かす
地域格差の改善や地方創生について、理解を深めたい方はこちらをお読みください。
関連記事:防災と地方創生で持続可能に|SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」
個人にできること

私たち一人ひとりの行動は、より安全に・移動しやすく・環境にやさしいまちづくりの実現に影響を与えます。ここでは、個人でできる取り組みを具体的に紹介します。
自分と家族を守る防災
自分や家族の命を守る一番の近道は、避難場所や家族の集合場所などを事前に確認しておくことです。
災害は突然発生し、停電・断水・交通のまひが同時に起こることがあります。家族で集合場所や連絡手段、防災グッズの保管場所など、共通ルールを事前に話し合っておきましょう。冷静に行動できるよう、家族で避難のシミュレーションをしておくことが重要です。
環境負荷が少ない移動
毎日の移動は、できる限り徒歩・自転車・公共交通を利用するようにしましょう。環境負荷が少ない移動手段を選択することは、温室効果ガス排出量の削減に効果的です。
車を利用する際も、まとめ買いをして移動回数を減らすなど、できることから行動することをおすすめします。
地域活動に参加
地域内で、日頃顔なじみのつながりである人が多いほど、災害時に行動しやすくなります。まちの安全や暮らしやすさを高めるためにも、季節のイベントや伝統行事など地域のイベントに参加することは重要です。
地域のイベントや清掃活動、避難訓練に参加するのが難しい方も、近所の人にあいさつすることから始めてみてください。
さらに、詳しく個人でできる事例を知りたい方はこちらも合わせてお読みください。
関連記事:SDGsの目標11と私たちにできること!海外事例も解説
【まとめ】SDGs11の目標を徹底解説しました

SDGs11の目標は、誰もが安心・安全に生活できるまちづくりを実現することを目指しています。最後に、目標11「住み続けられるまちづくりを」に関する5つの要点を確認しましょう。
- SDGs11は地域の安全と暮らしの質を高める枠組みである
- ターゲットは住宅、交通整備、防災、公共空間、環境保全など分野が多岐にわたる
- 日本は買い物難民、空き家の増加、災害からの回復力が課題である
- 家族での災害時ルールを決めたり、近所で顔見知りになったりしておくことが非常時の助け合い力を高める
- 環境への負担が少ない交通手段を選ぶように心がける
日頃の移動方法や家庭の防災などを見直し、持続可能なまちづくりの形成の一歩を踏み出しましょう。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











