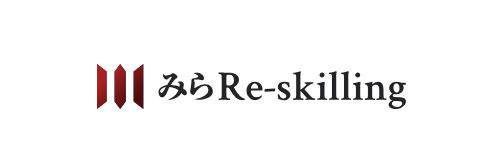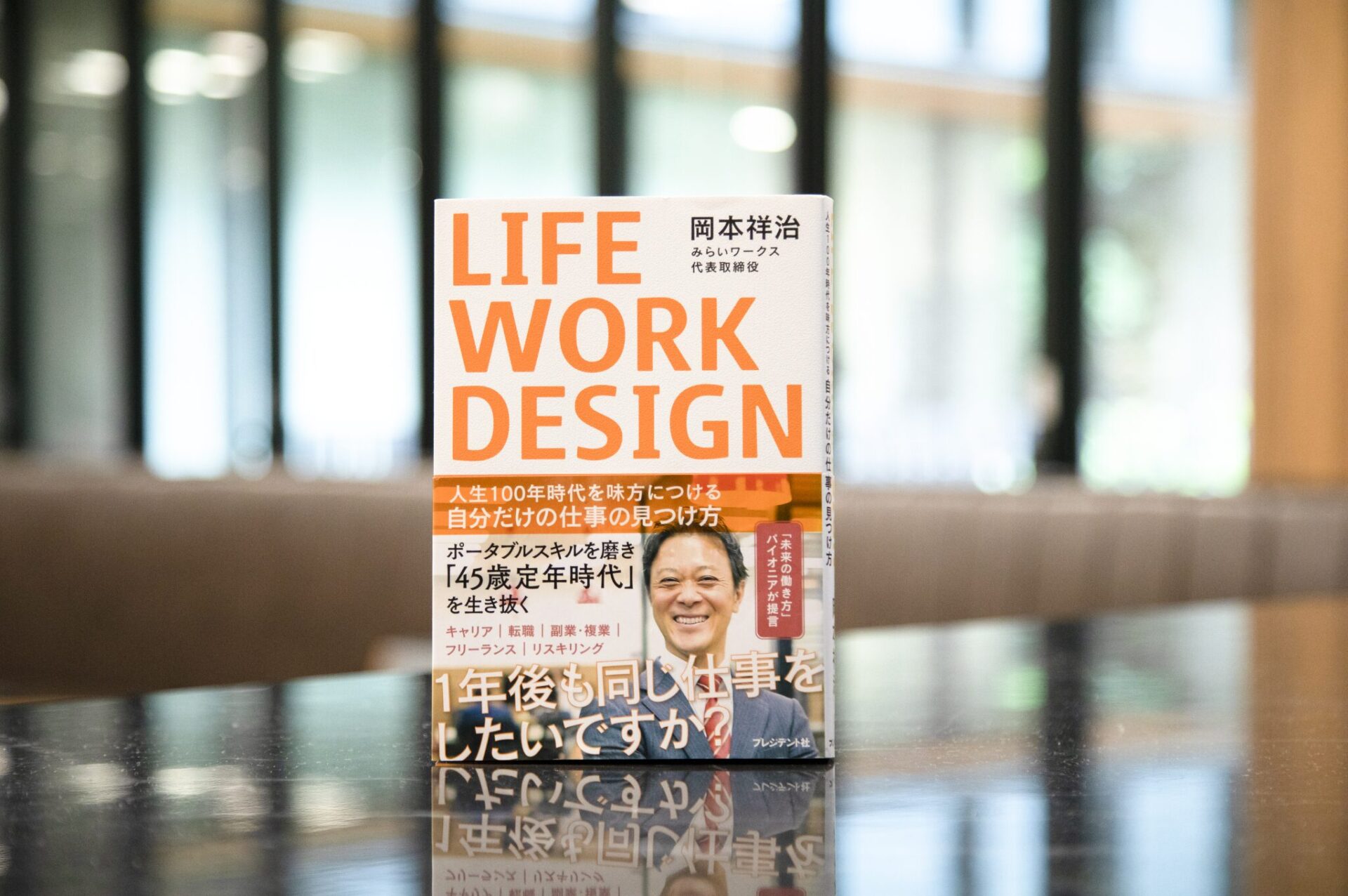地方創生に本気で挑む:みらいワークスが貫くビジョンと実践

フリーランス・副業・転職支援など、多様な働き方のプラットフォームを展開する株式会社みらいワークス。2025年3月には、GREEN NOTEを運営する株式会社Greennoteの親会社となりました。
同社は、ただ「働き方の選択肢」を提供するにとどまらず、創業以来「プロフェッショナル人材が挑戦するエコシステム」の創出を掲げ、個人のライスワークとライフワークを支援する仕組みを構築してきました。
そして、代表取締役社長の岡本祥治が一貫して掲げるテーマが「地方創生」。個人の想いや志がどのように事業へと昇華され、社会に変化をもたらしているのでしょうか。
その原点と実践、これからの展望を語りました。
プロ人材が挑戦できる社会を:みらいワークスのビジョンとは
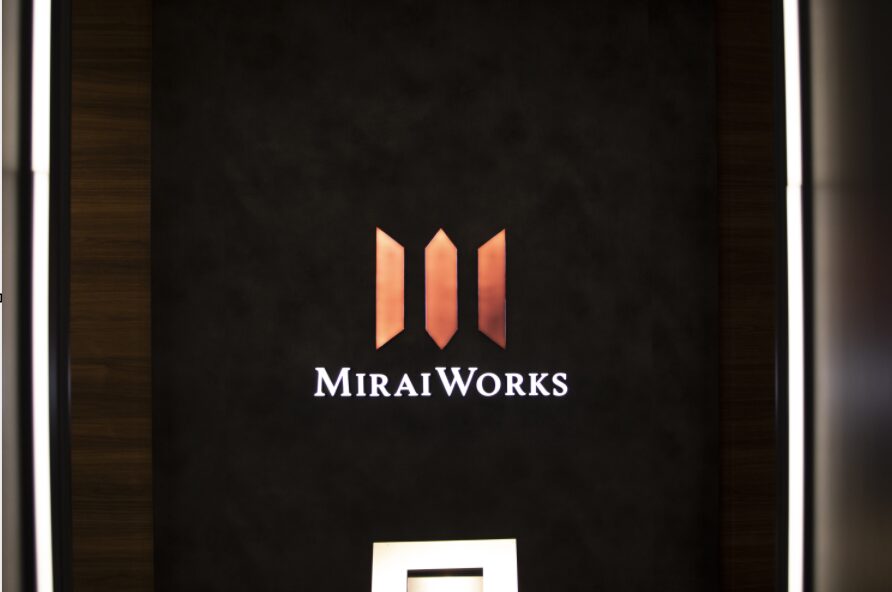
みらいワークスオフィスエントランス
編集部:みらいワークスとは一言でどのような会社か語ってください。
岡本:一言で言えば「プロフェッショナル人材の挑戦を支える会社」です。
われわれのビジョンは、「プロ人材が挑戦するエコシステムを創造する」というもの。大きく2つの視点があって、ひとつは「働き方の多様化」、もうひとつは「働く目的の変化」です。
もともと「働き方の多様化」に注目してきました。雇用だけではなく、フリーランス、副業、スタートアップへの参画、最近はリスキリング、つまり「学び直し」も含めて、多様な選択肢が当たり前になってきています。
こうした動きが加速したのは、ここ6〜7年くらいです。起業当初、「フリーランス」といっても、「フリーターと何が違うのですか?」と聞かれることが多々ありました。
しかし、最近は、社会の捉え方がだいぶ変わってきて、いろいろな働き方が自然に受け入れられるようになってきています。
それともうひとつ、われわれが大事にしているのが「働く目的」です。
みらいワークスの中では「ライスワーク」と「ライフワーク」という言い方をしていて、ライスワークは生活のための仕事、ライフワークは自分の人生で成し遂げたいことを指します。
どちらか片方ではなく、どちらにもしっかり取り組める社会をつくっていきたい、と。
そのための「社会インフラ」が、われわれが目指している役割です。

画像引用:みらいワークス公式サイト
個人のあり方が変わってくると、企業側も考え方を変えざるを得なくなります。
これまでは「雇用」という枠の中で、人材を確保するのが当たり前でした。しかし、今はひとつの会社の中だけで必要なスキルを保有する人材を育てるのが、難しい時代になっていると思います。
例えば、ここ数年で「デジタルトランスフォーメーション」という言葉が広まり、デジタル人材を育てようという動きが出てきました。
ところが、実際には多くの人材が一部の企業に偏っていて、なかなか社内にデジタル人材がいないのが現実です。
日本の転職市場は流動性が非常に低く、労働人口が6000万人以上いる中で、年間の転職者数はたった300万人くらいです。つまり5%程度にすぎません。
一方で、欧米だと10%以上は当たり前の世界。日本は人材が動かなくて、成長産業に人が回らない構造になってしまっています。
われわれがご紹介しているプロ人材は、常にリスキリングをしながらスキルを磨いている人たちです。
そういう人材に企業がいつでもアクセスできる社会にしていくこと。それが「挑戦するエコシステム」づくりの鍵です。
実際、そうした人たちと企業が一緒に仕事をするようになると、組織も自然とオープンになり、イノベーティブな文化が育っていきます。企業にとっても非常に大きなメリットです。
われわれは、こうした取り組みを通じて、個人を変え、組織を変え、ひいては社会全体を元気にしていく。そのような循環をつくっていきたいと、本気で思っています。
創業の原点にある「日本を元気に」:旅と気づきが導いた地方創生への思い

編集部:起業の原点や、みらいワークス創業に込めた想いを語ってください。
岡本:みらいワークスを立ち上げた原点には、「日本を元気にしたい」というシンプルだけれど強い想いがありました。
きっかけは、会社員時代の挫折でした。ある事件に巻き込まれて、社会的な立場を一度失ったとき、自分の存在意義を問い直すようになったのです。
当時、自分探しの一環として全国47都道府県を巡る旅に出ました。理系出身で歴史も地理もあまり知らなかった私ですが、実際に現地を訪れてみて、各地の人や文化、食に触れるたびに「日本って、すごくいい国だな」と気づかされました。
しかし、一方で、経済的には厳しい現実があります。
駅前の商店街はシャッター通りになり、郊外のバイパス沿いには大型ショッピングモールがぽつんと繁盛しています。地域経済が徐々に大資本に飲み込まれていく様子を見て、非常に違和感がありました。
競争や効率だけを優先する社会が、日本らしさや地域の豊かさを奪っているように感じたのです。
そのようなモヤモヤを抱えながら旅を続ける中で、青森のねぶた祭りに出会いました。
その熱量、地域の人々が1年を全て祭りに命をかける姿に触れて、「自分は何をしているのだろう」と深く突き動かされたのです。
その瞬間、「日本を元気にする仕事がしたい」と腹を括って、帰京後すぐに起業を決意しました。

青森県のねぶた祭り|iStock | PixHound
ただ、現実は甘くなく、創業直後にリーマン・ショックが起き、まず食べることが先だと、東京でフリーランスとして働くことにしました。
ありがたい話に、しばらくすると自分では対応しきれない程、お仕事をいただけるようになっていました。
しかし、ふと周りを見てみると、同じように挑戦したいのに環境が整わず苦しんでいるフリーランスや起業家の仲間たちがいました。
そこで自分が対応しきれない仕事を彼らに紹介し始めたのです。すると、みんな非常に喜んでくれて、「これが自分のやるべきことかもしれない」と思うようになりました。
当初は「ライスワーク」の支援が中心でしたが、やがて「地方創生こそ、みんなのライフワークだ」と気づきました。
そして始めたのが、地方副業マッチングの「Skill Shift」や、自治体や金融機関と連携した地方転職支援「Glocal Mission Jobs(GMJ)」です。
私自身の原体験から生まれた「地方を元気にする挑戦」が、今多くのプロ人材の挑戦にもつながっています。
ライスワークからライフワークへ:挑戦のきっかけを地域に届ける
編集部:みらいワークスが実施してきた地方創生に関する具体的なプロジェクト事例を語ってください。
岡本:われわれが地方創生で最初に本格的に取り組んだのが、2020年に岡山市と一緒に行った副業人材のマッチング事業です。
自治体が都市部のプロ人材を“副業”として公募する取り組みでした。蓋を開けてみたら、600人以上が応募してくれました。
中には、大手エンターテインメント企業の現役ブランディングマネージャーや元外資系大企業のマーケターといった、プロ中のプロが手を挙げてくれたのです。
ある人は、両親が岡山出身で、地元に何か恩返しをしたい気持ちが以前からあったそうです。
他にも、外資系大手コンサルティング企業の通信部門でバリバリ活躍されている方が、岡山出身で「地元のために何かしたい」という想いで、週1で岡山市役所に通い、地域のDX支援や地元企業との連携に尽力してくれました。
そうすると、そこから人の縁が広がって、地元銀行のグループ会社に、また別の外資系大手企業出身者が社長として入る展開もあったのです。
1人の副業が、地域とのつながりを生んで、さらに次の人材が動く。そのような芋づる式の広がりが起きました。
われわれが提供したのは、ほんの小さな「挑戦のきっかけ」にすぎないです。しかし、その一歩があるだけで、プロ人材のライフワークが動き出します。
実力も意欲もある人たちが、「地元のために何かしたい」と思っていました。しかし、どう動けばいいか分かりませんでした。そういう人に最初の接点をつくるのが、われわれの役割です。
今では、金融機関は120社以上、自治体も100以上と連携していて、各地につながりの土壌ができています。
最近では、NTT東日本と長野でDXのプロジェクトを展開したり、ANAシステムズと地域で実践型リスキリングの取り組みをしたり、大企業との連携も広がっています。
結局、個人にとってのライフワークと、企業にとってのCSRやESGは、意味のある挑戦を通じて、社会と関わっていく点でとても似ています。
それを一緒にかたちにできるようになってきたのは、本当にうれしいことだと思っています。
リスキリング×地方課題:企業と地域の未来を変える“実践型学び”の可能性
編集部:人材紹介業に加えて、地方と絡めて展開しているリスキリングという人材育成事業についても語ってください。
岡本:リスキリングの事業は、2020年から始めました。
当時はまだ「リスキリング」という言葉もなく、われわれは「HRソリューション」と呼んで、大企業の人材開発をテーマに動き始めました。
きっかけは、「挑戦するプロ人材を増やす」という自分たちのビジョンに立ち返ったときに、年収800万円以上のハイスキル層、つまり労働人口の約11%の人たちのほとんどが大企業に勤めていると気づいたことでした。
それであれば、こちらから乗り込んで行き、大企業の中で眠っているプロ人材を解放していく必要があると感じました。
一方で、地方創生事業を続けていくと地方の課題が大量の情報として集まってきました。
あるとき、福島の自治体から「ワーケーションをやってほしい」と相談を受けたので、普通のワーケーションではなく、課題解決型にしようと思ったのです。
東京のサラリーマンに現地へ行ってもらい、最初の数日は現地を回り、地元の方々から実際に地元の事情や課題について話を聞かせていただいた上で、最後の2日間で「地元の日本酒を若者や海外にどう広めるか」というようなテーマでプレゼンをしてもらいました。
最後に地元の人から感想をいただくと、普段の仕事スキルが地域のために生かせる成功体験を得られて、参加者の目が本当にキラキラしたのです。
「これは、リスキリングになる」と確信し、実践型リスキリングとしてサービス化しました。
ある企業の方はメンバーと一緒に実践型リスキリングで地域へ行って、仲も深まり、更に次のプロジェクトの受注にもつながっています。
そのような良い循環が生まれていて、われわれの主力事業のひとつになりました。かたちになるまで5年ほどかかりましたが、本当にやってきてよかったと思っています。
ロマンとソロバンの両立:持続可能な地方創生モデルの追求

編集部:リスキリングや地方創生といった社会課題に取り組む中で、どのように企業としての収益性と社会的意義を両立させているのか、具体的な取り組みや考え方を語ってください。
岡本:われわれの会社ではよく「ロマンとそろばん」と言うのですが、ロマンはビジョンの実現、そろばんは利益のことです。両方がそろわないと持続的な活動とはなっていきません。
ですから、われわれは利益を出すことにもこだわり、その上でビジョンに向かって走り続けています。
単なる社会貢献ではなく、きちんと収益につながる仕組みとして行っています。
GDPの6割以上を占める地域経済を活性化することは、日本経済を元気にするためには必要不可欠なことです。
ライフワークとして地方創生に取り組みたいプロ人材の方も多いため、われわれのビジョンの実現に向けて、地方創生事業を行うことはとても意義があります。
しかし、地方創生事業で大きく稼ぐことは困難です。
そこで、われわれは、この地方創生事業をやることによって、地域の課題が毎月のように100件以上集まってくるため、これを先ほどお伝えしたリスキリング事業として、大企業向けソリューションとして提供するようになりました。
これにより、われわれのメインのフリーランス事業の収益アップ、クロスセルによって収益アップにもつながるということで、地方創生事業という、いわゆるロマンでおこなっていることを、そろばんに転化することに成功しております。
みらいワークスが描くグローバル人材×地方創生の次なる一手
編集部:今後、地方創生関連で新たに仕掛けたい事業の構想はありますか。
岡本:今期に入り、「グローバル人材開発室」という新しい部署を立ち上げました。キーワードは「グローバル人材×地方」です。
私は、これまでに111カ国くらい旅をしてきましたが、世界中に「日本が好き」と言ってくれる人は、本当に大勢いるのです。
その人たちをどうしたら日本経済に生かせるか考えています。
特にデジタル人材は、今は東京のベンチャーくらいしか受け入れていない状況です。
しかし実際は、海外の方の多くは地方に興味を持っている人が多いので、東京よりもむしろ地方の方が、フィットする可能性があります。
今考えているのは、地方に各国のコミュニティをつくることです。
コンソーシアムに参加する企業や現地の自治体と一緒に住環境や就業機会を整えて、住みながら働きながら日本語を覚えてもらうような長期スパンでの仕掛けを構想中です。
地域に来た海外の人たちが、日本語を覚えて、日本の文化も理解してくれたら、将来その人たちが母国に戻って、そこから日本企業と一緒に何か事業を行うことも起こり得るでしょう。
そうすると、地域の企業も、自然とグローバルマインドを持つようになりますし、新しいつながりが生まれていくと思います。
「人の行き来があるローカル」という流れができたら、地方創生にも新しい風が吹くと思いませんか。
そのような未来を見越して一緒にやってくれる自治体さんがいれば、ぜひお声掛けいただきたいと思います。
「地域には“宝”がある——都市とつながる新しい地方創生のかたち

編集部:最後に読者の方に向けて、地方創生と絡めてこれからの働き方についてメッセージをお願いいたします。
岡本:いろいろな地域で見てきて思うのは、自分の地元の良さに、地元の人が気づいていないことです。
あまりにも当たり前すぎて、輝いて見えないのです。しかし、どのような地域にも必ずいいものがあり、それをさらに輝かせてほしいと思っています。
ただ、地元の人たちだけでやろうとすると、どうしても限界があります。
だからこそ、都市部にいるプロデューサーやクリエイター、地域に関わりたいと思っている人たちの力を借りて、一緒に新しい価値をつくっていくことを願います。
勇気を出して、外の人たちに助けを求めてみてほしい、と。きっとそこから、地元に眠っていた魅力が再発見されて、まったく新しい地域の未来が見えてくるはずです。
結果的には、日本経済全体を底上げしていく動きにつながっていくと思います。
「自分たちの地域には何もない」と思わずに、まずはその一歩を踏み出していただければ。そこから始まる変化が、次の未来をつくっていくはずです。
編集後記
岡本の語る「地方創生」は、単なる地域活性化ではありません。
個人の挑戦と成長、企業の社会的責任、地域経済の再興といった複数の文脈を丁寧につなぎながら、持続可能な社会のエコシステムを構築する取り組みです。
岡本の「地方創生は社会貢献ではなく、真に日本経済をよくするための必然」とする姿勢。その根底にあるのは、社会からこぼれ落ちそうになった原体験と、全国を巡る中で得た地域への共感、そして目の前の仲間を支えたいという純粋な動機でした。
ロマンとソロバンを両立させ、ビジョンと事業の接続を実現するみらいワークスの挑戦は、これからの地方創生のあり方に一石を投じるものです。
本インタビューではご紹介しきれなかった岡本の想いは、書籍でも紹介しています。
ぜひ、手に取ってインタビューの続きをお楽しみください。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!