SDGs4の問題点とは?世界の教育現場の現状と向き合おう

SDGs4の目標は「質の高い教育をみんなに」です。世界中の子どもから大人まで、誰もが平等に学ぶ機会を得て、質の良い教育を受けられる社会を目指しています。
しかし現実には、国や地域によって教育にまつわる多くの課題が生じています。その背景にあるのは、「SDGs4の目標そのもの」に対する問題点です。
本記事ではSDGs4の問題点に焦点を当て、日本を含む世界の「教育現場で今何が起きているのか」と「質の高い教育をすべての人に届けるためにはどうしたら良いか」を考えます。記事の後半では国内外の成功事例も紹介しているので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
SDGs4「質の高い教育をみんなに」の概要

SDGs4では、2030年までにすべての子どもが「無償かつ公平で質の高い教育」を受けられることを目的としています。さらに注目したいのは、「仕事に関係する技術や能力をそなえた若者やおとなをたくさん増やす」という目標です。
SDGs4は子どもの教育だけでなく、大人が仕事に必要な技術や知識を身に付けるための教育も必要だとしています。「教育」と聞くと子どもに対する教育をイメージしがちですが、SDGs4ではすべての人に対する生涯学習の大切さを訴えています。
SDGs4:10のターゲットとは

SDGs4には、以下の10個のターゲットがあります。初等教育の普及から高等教育の拡大、職業教育、ダイバーシティやジェンダー平等の推進まで、多岐にわたる内容が盛り込まれています。
| ターゲット番号 | 内容 |
|---|---|
| 4.1 | 2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 |
| 4.2 | 2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 |
| 4.3 | 2030年までに、すべての人々が男女の区別なく、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 |
| 4.4 | 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 |
| 4.5 | 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 |
| 4.6 | 2030年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 |
| 4.7 | 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 |
| 4.a | 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 |
| 4.b | 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 |
| 4.c | 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。 |
世界の教育現場では何が起きている?

教育は、世界中すべての子どもに当たり前に保障されるべきものです。しかし現実は、地域や経済状況によって大きな差が生じています。海外と日本の教育現場を比較し、SDGs4の問題点を具体的に見てみましょう。
海外の教育の現状と問題点
ユニセフによると、サハラ以南のアフリカでは、5人に1人の子ども(6〜11歳)が小学校に通えていません。対象範囲を「世界」「5歳から17歳の子ども」に拡大すると、実に3億3,000万人以上が学校に通えていないといわれています。
関連記事:3億人以上が学校に通えていない現実|SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」
学校に通えないと、読み書きができないことで職業の選択肢が狭まってしまいます。すると低収入の仕事にしか就けず、いつまでも貧困から抜け出せない負のサイクルに陥ってしまいかねません。
世界には7億7,500万人もの非識字者がおり、その約3分の2が女性だといわれています。国別のランキングで識字率が低い国である南スーダン・ニジェール・中央アフリカ共和国の3カ国も、サハラ以南アフリカに位置しています。「女性には教育は必要ない」との考えが根強い地域もあるなど、ジェンダー格差も問題です。児童婚や望まない妊娠によって教育の機会を断たれ、家事や育児に専念する女性もいます。
政治的・経済的に不安定な国々では、紛争や貧困、地理的制約によって通学ができず、教育環境が失われることも少なくありません。教育への投資が後回しにされ、学校数や教員不足などさまざまな問題が生じています。
参考:プラン・インターナショナル|識字率とは?国別の現状や識字率が低い原因、生活にもたらす影響
日本の教育の現状と問題点
一方で、日本は教育水準が高い国とされており、SDGs4に関する問題点はないように見受けられます。しかし、SDGs4の問題点は残念ながら日本にも存在します。
問題点の1つ目は教育格差です。例えば、家庭の経済格差によって塾に通えない、質の高い学校へ進学できないといった、学習環境の差があります。また、少子化により児童数が少なく、廃校となる学校も増加しています。
問題点の2つ目は、不登校やいじめにより教育機会を失う子どもの増加です。2023年度のいじめの認知件数は約73万件、不登校児童は約35万にものぼり、過去最多となりました。
3つ目の問題点として、教員不足も挙げられます。2026年度採用の教員採用試験では、志願者数が増加した自治体はわずか17で、多くの自治体で減少傾向が見られました。特に深刻なのが小学校教員で、少なくとも39の自治体で志願者数が減少しています。要因として挙げられるのは、教員に対するイメージの悪化です。長時間労働やサービス残業、過労死、いじめ、モンスターペアレントといった問題が社会問題になり、「教員=ブラック」のイメージを持たれるようになりました。
こうして見ると、教育が進んでいると思われる日本でも、問題点が多いことが分かるでしょう。
世界と日本の教育格差は、以下の記事でも取り上げています。SDGs4の問題点を象徴する教育格差について、さらなる理解を深めましょう。
関連記事:世界で広がっている教育格差|その現状とSDGs達成への取り組み
参考:読売新聞オンライン|不登校の小中学生が過去最多34万人超…コロナ禍で急増し、その後も増え続ける
参考:教育人材センター|[2026年度採用]教員採用試験志願者の状況は?
SDGs4の問題点

SDGs4は教育の大切さを世界に示しました。しかし、指標や定義のあいまいさにより、批判や問題が発生しています。
本項では、SDGs4の「目標そのもの」の問題点に着目してみましょう。
指標・制度設計上の限界
SDGs4の問題点の1つに、統一された指標やターゲットが存在しない点が挙げられます。「教育の質」の定義が国や地域で異なるためです。就学率や識字率だけでは、真の意味での教育の質を把握できません。
国による収集データの不均衡や、国間で比較する難しさも問題です。現状の制度設計では、目標達成の進捗度合いを正確に評価できないのみならず、「報告すること」が目的化するリスクがあります。
参考:Institute of Development Studies|SDG 4 Education: Necessary ambition or misplaced folly?
「質の高い教育」の定義があいまい
別の問題点としては、「質の高い教育」の定義に明確な基準がなく、解釈が国によって異なる点です。例えば、義務教育制度が整備され識字率の高い日本では、IT人材の育成やグローバル人材に関する教育を「質の高い教育」と定義するかもしれません。他方、学校に通えない子どもの多い南アジアやアフリカ諸国では、基礎的な識字教育の普及を第一に掲げるでしょう。
このように、SDGs4には目標そのものに対する問題点が指摘されており、制度設計の見直しや改善が求められています。
SDGs4の問題点を克服するには
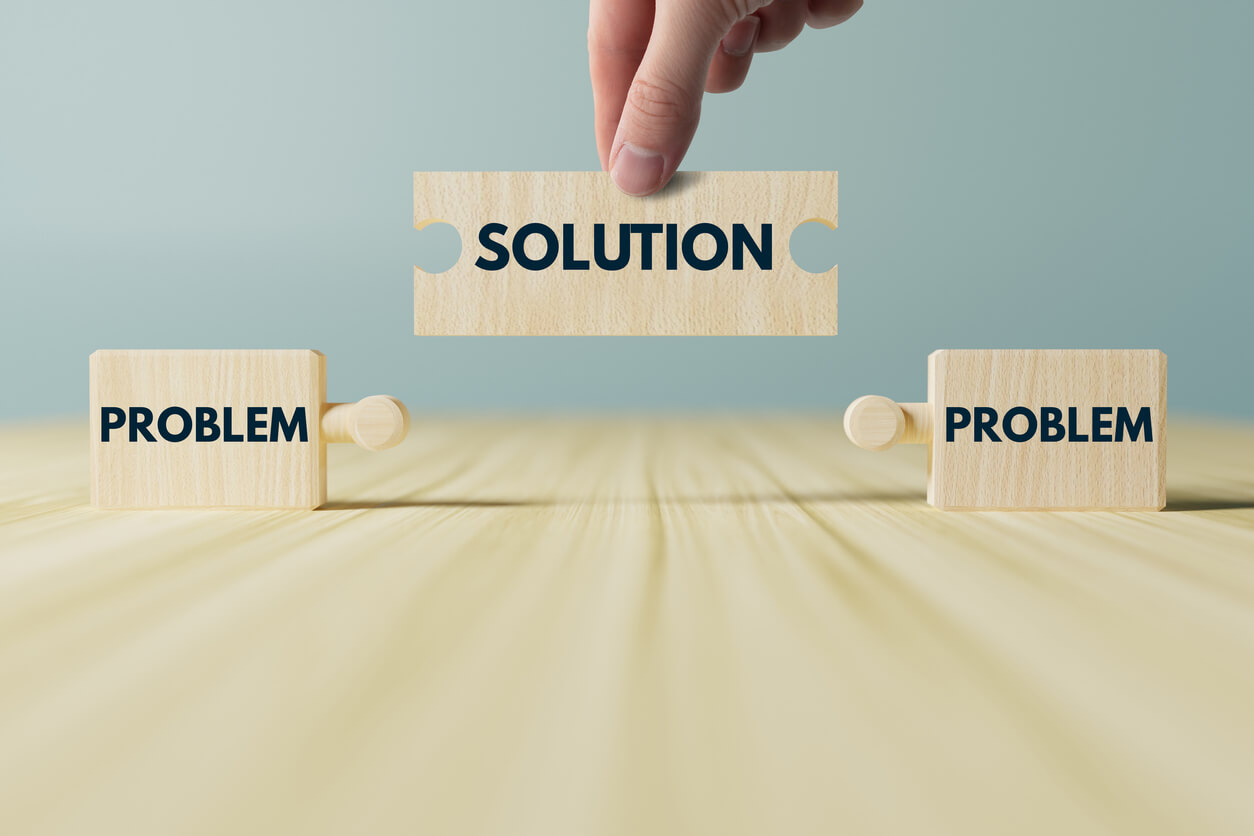
世界の教育現場の現状や、SDGs4の問題点を見てきました。これらの問題点を改善するためには、どのような取り組みが必要でしょうか。考えられる3つの対策を紹介します。
新指標の整備
まず1つ目は、指標そのものを新しくし、各国の教育の成果を公平に測ることです。例えば、OECD(経済協力開発機構)が2000年より3年ごとに実施している、PISA調査が挙げられます。義務教育終了段階である各国15歳の生徒を対象に、身に付けてきた知識や技能を実生活でどの程度活用できるかを測る試験です。
世界各国の子どもが同じ条件でテストを受験し、同じ指標で採点されるため、国・地域間の比較や自国の相対的位置の把握が容易にでき、国レベルの教育課題を経年比較するのに役立ちます。
教員の負荷軽減と待遇改善
2つ目は、教育現場の働き方改革です。日本の教員における1週間の勤務時間は小学校教員が54.4時間、中学校教員が56時間と、OECD加盟国(※)の平均38.3時間と比較して15時間以上も多くなっています。
OECD(※):「経済協力開発機構」の意。ヨーロッパ諸国、日米を含め38カ国の先進国が加盟する国際機関。日本は1964年に加盟。経済成長、貿易自由化、途上国支援の3つに貢献することを目的として設立。
また、2023年の日本の教員給与は4万7,349ドルで、OECD加盟国平均の5万3,456ドルを6,107ドル下回る結果となっています。業務量が多く勤務時間が長いわりに、給与が低い点が問題です。教員の負荷軽減と待遇改善は、急務で進める必要があるでしょう。
参考:東洋経済オンライン|世界でも突出した長時間労働、「教員の働く環境」日本と他国の決定的差 国際比較調査から見える日本の「リソース不足」
参考:朝日新聞|日本の教員給与、OECD平均下回る「待遇面への投資で魅力向上を」
教育レジリエンスの強化
最後に、自然災害や紛争、感染症などによる学校閉鎖に対応できる仕組みも不可欠です。
コロナ禍では、多くの学校が臨時休校になりました。低所得世帯やひとり親家庭では、塾やオンライン学習などの代替的な教育手段を整えることが困難で、学習格差が拡大したとのデータがあります。低所得世帯が利用しやすい奨学金、オンライン教育ツール、学習支援制度の整備など、収入や環境の変化によって教育が制限されない基盤を構築する必要があるでしょう。
教育に関するレジリエンス(※)を強化することは、SDGs4の問題点を乗り越える鍵となります。
レジリエンス(※):困難な環境にうまく適応したり、精神的に落ち込んだ状態から回復したりする力。「たくましさ」とともに、逆境に柔軟に対応する「しなやかさ」も兼ね備えた力を指す。
参考:経済産業研究所|新型コロナは教育格差にどのような影響を及ぼしたのか?
SDGs4「質の高い教育をみんなに」国内外の成功事例

SDGs4の問題点を克服するために、各国のさまざまな機関や企業が取り組み、成果を上げています。JICA(独立行政法人国際協力機構)と日本のIT企業であるSCSK社の事例を見てみましょう。
JICA:開発途上国における教育課題の改善に大きく貢献
まずは主に開発途上国への国際協力を行っている、JICAの取り組みを2つ紹介します。
1つ目はエルサルバドルでの「算数・数学科の指導力向上プロジェクト(ESMATE)」です。
初・中等教育における教科書と教師用指導書の開発や、教員養成課程の支援を実施しました。結果、児童の学力平均が向上する成果を上げており、他中南米諸国への導入も期待されています。
2つ目は「みんなの学校プロジェクト」です。保護者や教員のみならず、地域住民が一丸となって、子どもの学習環境を改善していくプロジェクトです。
ニジェールから始まったみんなの学校プロジェクトは、アフリカ8カ国、約5万3,000校の小中学校へと広がりました。「教育」だけにとどまらず、学校給食や衛生管理にまで活動が拡大しています。
参考:JICA|事業事前評価表
参考:JICA|進化する「みんなの学校」プロジェクト:アフリカ8ヵ国5万3000校に拡大、学校給食や手洗い啓発にも発展
SCSK:リカレント教育で社員の学び直しを徹底サポート
SCSKは、リカレント教育(※)に力を入れているIT企業です。
社員の自己研さんをサポートする施策として「コツ活」を導入し、学びの活動事例を社内で共有することで、社員同士が高め合う文化を醸成しています。業務外での学びには全社員に月額5,000円の手当を支給し、活動実績に応じて図書カードや学びコンテンツの提供を行うなど、充実した内容です。
こうした取り組みが評価され、経済産業省発行のリカレント教育事例集でも紹介されています。
リカレント教育(※):学校教育を終え社会に出たあとも、新たな知識やスキルを学び直し仕事に生かしていくこと。「リカレント」は何度も繰り返されることの意で、一度きりではなく社会人としてのスキルやキャリアの持続的な向上を目指す。
参考:SCSK公式サイト
参考:経済産業省|イノベーション創出のためのリカレント教育事例集
まとめ

SDGs4の問題点は「教育の質」の定義の難しさにより、各国での対応に齟齬(そご)があることです。制度設計の見直しとともに、教育レジリエンスを強化していく必要があります。また、教育が普及していると捉えがちな、日本での問題点にも目を向けることが大切です。
教育は人々の未来に直結する問題です。職業選択や貧困、ジェンダー平等、ダイバーシティなど、SDGsのほかの目標とも深く関わっています。現状を知り、問題に目を向け、1つずつ解決していくことで、持続可能な社会を築いていきましょう。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











