子どもの権利とは?基本概念や日本における課題と取り組みを徹底解説

子どもの権利は、世界中のすべての子どもに対して「当たり前に」保障されるべき大切なものです。国際的な約束として「子どもの権利条約」があり、日本も1994年に批准しました。しかし、いじめや虐待の問題が残り、十分に守られていない現実もあります。
本記事では、子どもが有する権利や子どもの権利条約の基本内容から、日本における現状や課題、子どもの権利を守る具体的な取り組み事例、そして私たちが実践できる行動を分かりやすく解説します。
子どもの権利とは?

すべての子どもは、安心して生活できる権利をもっています。子どもの権利に関する国際的な取り決めが、子どもの権利条約です。2025年時点で世界196カ国が批准(※)しています。条約には基本理念と子どもの具体的な権利が書かれており、各国に取り組みを求めています。
批准(※):条約に対する国家の最終的な確認、同意のこと
子どもの権利条約の成り立ちと日本の批准
第二次世界大戦の終戦後、すべての人がもつ人権が注目されるようになりました。すると、社会で弱い立場である子どもの人権に対しても、徐々に関心が高まっていきます。
人権問題はSDGsの根幹です。以下の記事では、人権に関わるSDGsや、日本での人権問題を取り上げています。ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:人権問題とSDGs!4つの目標を達成するために考えるべき「課題」
子どもの権利条約は1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に世界で158番目に批准しました。子どもの権利条約は世界で最も多く批准された人権条約であり、日本でも子どもの権利に関する法制度や取り組みの土台になっています。批准国は、条約の実現に向けて定期的に国連へ報告する義務を負います。
子どもの権利条約の4つの柱と4つの原則
子どもの権利条約には、以下の4つの柱があります。
- 生きる権利:住む場所や食べ物があり、必要な医療を受け、命を守られる権利
- 育つ権利:教育を受け、家族と一緒に生活し成長する権利
- 守られる権利:虐待や搾取、有害な労働などから守られる権利
- 参加する権利:自由に意見を表し、成長に必要な情報を提供され、有害な情報からは守られる権利
さらに、子どもの権利条約には次の4つの原則があります。
- 差別の禁止
- 子どもの最善の利益
- 生命・生存・発達の保障
- 子どもの意見の尊重
子どもの権利を侵害している例としてイメージしやすいのは、児童労働です。発展途上国ではもちろん、日本でも児童労働は起きています。以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:JKが考えるSDGs|児童労働って何が問題なの?その問題点と取り組みについて
子どもの権利条約では、子どもは「弱くて大人から守られる存在」だけではなく、「ひとりの人間として人権(権利)をもっている」との考え方を示しています。「子どもは成長の過程にあり、大人からの保護や配慮が必要なのと同時に、ひとりの人間としてさまざまな権利をもっている」とするのが、子どもの権利条約の特徴です。
参考:ワールドビジョン|子どもの権利と権利条約をめぐる動きや問題点を誰にでもわかりやすく解説
日本における子どもの権利への取り組みと課題
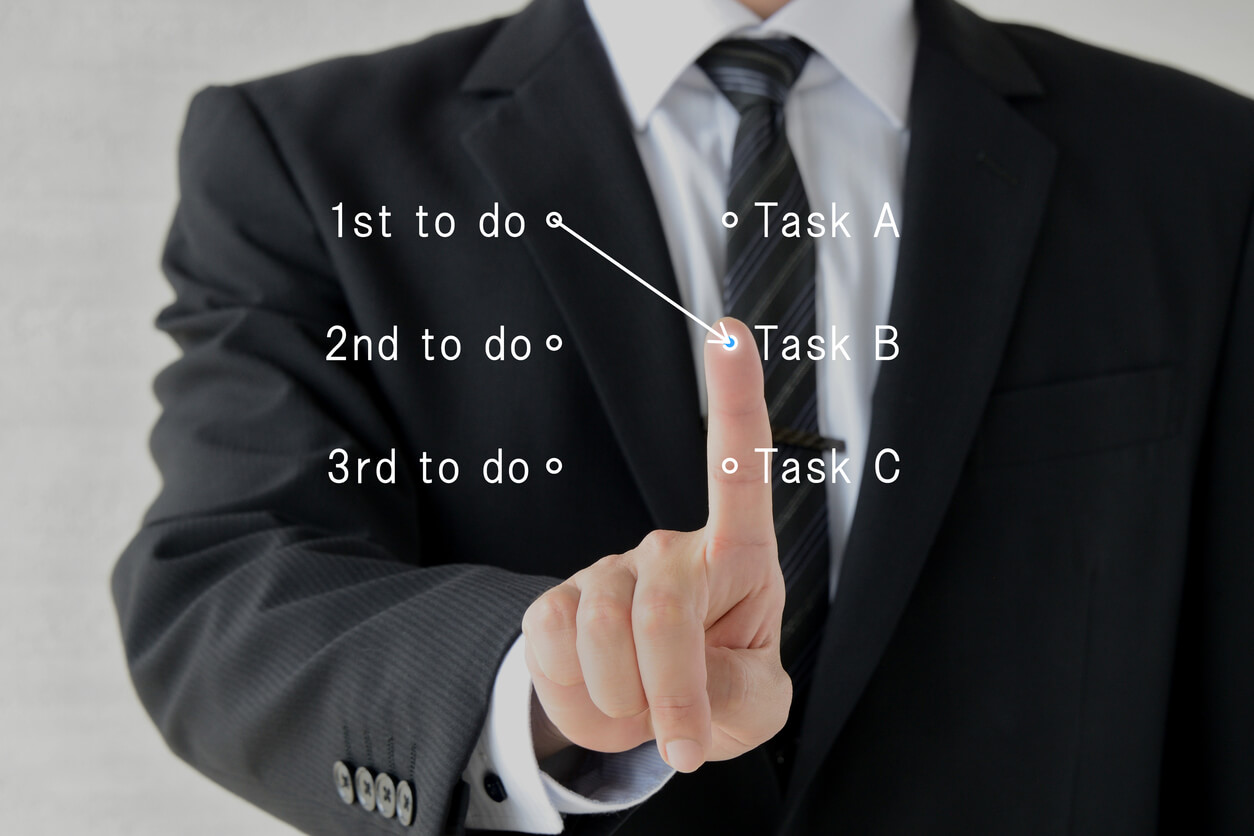
日本政府からの定期報告に対して国連子どもの権利条約委員会は、改善すべき点の勧告を行います。
以下は、2019年に出された改善点の一例です。
・子どもの権利に関する包括的な法律の採択
・虐待や性的暴力を受けた子どものための使いやすい申し立ての仕組みの設置
・貧困を減らすための戦略強化
・学校におけるいじめ防止キャンペーンの実施
特に虐待やいじめは深刻な問題です。2023年度の虐待の認知件数は約23万件、いじめの認知件数は約73万件にのぼり、過去最多となりました。権利を守るための制度は整いつつありますが、実態が伴っていない点が課題です。
参考:セーブ・ザ・チルドレン|Vol.1「子どもの権利条約」報告審査のプロセスとは?
学校現場における子どもの権利教育の現状と課題
長年、子どもの権利に関する授業は日本の学校教育では行われてきませんでした。理不尽な校則、いわゆるブラック校則も社会問題となっています。例えば、地毛がもともと明るい生徒がたびたび黒染めを要求され不登校になるなど、人権侵害とも捉えられる事例もあります。
教員の大半が、子どもの権利条約の内容を十分に理解していません。教育現場での認知度不足は、子どもが自分の権利を理解・主張する機会を奪います。世界と比較して日本の学生は主体性が低く、自分の意見を発信することを好みません。「目立って周囲から浮きたくない」「声をあげても何も変わらない」と考える学生が多いからです。こうした意識の形成には、日本の教育が影響しているといえるでしょう。
参考:東京都立大学大学院 客員教授 宮下与兵衛|学校における子どもの権利の実態と学校運営への子どもの意見表明権の保障
こども家庭庁の設置とこども基本法の制定
こうした問題を受けて、2023年にこども家庭庁が発足し、同時にこども基本法が制定されました。こども基本法では子どもの権利を尊重し、すべての子どもが自分らしく幸せに暮らせる社会の実現を目指しています。国や都道府県、市区町村はこども基本法の内容にそって、子ども施策(子どもに関する取り組み)を進めています。
子どもの権利を守る具体的な取り組み事例

子どもの権利は世界中で脅かされており、子どもの権利を守るための取り組みが幅広く行われるようになりました。政府機関やNGO団体などが協力し、地域に根ざした取り組みが実践されています。次項で具体例を見てみましょう。
ワールド・ビジョンやNPO法人による支援活動
国際NGOワールド・ビジョンは、主に貧困地域で活動する団体です。世界中すべての子どもが可能性を十分に開花できるよう、教育支援を行っています。校舎の建築・修復、難民の子どもたちのための学校運営、補習授業の開催、教員の養成・研修、女子の教育の啓発活動などを通じて、教育を受ける重要性を伝えています。
日本のNPO法人であるかものはしプロジェクトは、カンボジアとインドで子どもの人身売買をなくす活動に取り組んできました。2019年より日本でも活動を開始し、妊産婦の支援、児童養護施設を出た若者の応援、子どもや養育者にやさしい地域づくりに取り組んでいます。
法務省の人権啓発活動
法務省の人権擁護機関は、子どもの権利を理解してもらうため、さまざまな啓発活動を行っています。人権尊重の大切さや基本的人権の理解を深めることを目的に、昭和56年度から全国中学生人権作文コンテストを実施しています。2024年度は74万近くもの応募が集まりました。
主に小学生を対象に、人権教室や人権の花運動を実施しています。いじめなどの人権問題を考えたり、花を協力し育てることで生命の尊さを実感し、思いやりの心を育む機会を提供したりしています。
参考:法務省|啓発活動
子どもの権利を守るために私たちができる取り組みとは

子どもの権利を守るためには、政府や学校だけでなく、私たち一人ひとりの行動が重要です。子どもの権利への理解を深め、実際に行動することで、公平で安心できる社会が築けます。私たちにできる取り組みは何かを考えてみましょう。
子どもの権利条約の理解と情報発信
まずは、子どもの権利条約を正しく理解することが大切です。ユニセフのウェブサイトやこども家庭庁の資料を活用して理解を深め、家庭や職場で話題に出してみましょう。
SNSを活用し発信することも有効です。情報が拡散されることで、子どもの権利を守る取り組みが広がります。
寄付やボランティアで支援団体をサポート
支援団体を資金面や活動面で支えることも効果的です。少額の寄付や地域のボランティア活動は、大きな力となります。
例えば、先に述べたワールド・ビジョンやかものはしプロジェクトも、スポンサーを募集しています。ワールド・ビジョンの「チャイルドスポンサー制度」は月額4,500円、「プロジェクト・サポーター」なら月額1,000円で途上国の子どもを支援できます。1回限りの寄付も可能です。かものはしプロジェクトでも、月々1,000円からの寄付を募っています。内容や予算に合わせて、寄付する団体を探してみてください。
子ども自身が自分の権利を学び理解する
子ども自身が自分の権利を知ることも大切です。学校での授業や地域のイベントを通じて、子どもたちが自分の意見を大切にする力を養いましょう。子どもたちが臆せず声を上げられるようになることで、子どもの権利を守る文化が広がります。
以下のリンクでは、子どもの権利に関するイベント情報が発信されています。オンラインで視聴可能なものや個人でも参加可能なものもあるので、親子で参加してみてはいかがでしょうか。
まとめ

子どもの権利は、すべての子どもに平等に与えられる基本的人権です。日本でも法律や制度が整備されてきましたが、いじめや虐待など解決すべき課題が残っています。
国や自治体、NPOだけでなく、私たち一人ひとりが子どもの権利を理解し、取り組むことが重要です。子どもが安心して暮らせる社会を、一緒に築いていきましょう。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











