山村留学の費用と実態!後悔を防ぐための事前準備

都市部で子育てをしていると、「自然体験が足りない」「自然豊かな環境で子育てをしたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、子どもが自然の中で学び、成長できる「山村留学」の魅力や費用、選び方のポイント、成功のためのステップを詳しく解説します。後悔しない山村留学のコツが分かるはずです。ぜひ、ご覧ください。
山村留学とは?都会では得られない教育

「山村留学」と聞くと、自然体験と何が違うのか疑問に思う方もいるかもしれません。まずは、山村留学の概要を詳しく解説します。
山村留学とは
山村留学とは、義務教育期間中の子どもが一定期間、山村地域で生活や学習、自然活動を体験するプログラムです。自然豊かな環境での生活を通じて、子どもの自立心や協調性、自然への理解を育むことを目的としています。山村留学には、主に4つの形態が挙げられます。
- 家族型:親子で山村地域に移住し、子どもは地域の学校に通う
- 里親型:ホームステイのように里親家庭に預けられ、子どもは地域の学校に通う
- 寮型:寮に宿泊し、子どもは地域の学校に通う
- 親戚型:留学先の親戚宅から、子どもは地域の学校に通う
農業体験や野外活動などを通じて、自分で考えて行動する力が育まれるだけでなく、地域住民との交流を通じて、人間関係の大切さも学べます。普段都会で暮らす子どもたちにとって、自然の中でのびのびとした体験は新鮮で、価値観を広げられる貴重な機会です。
また、山村留学は、地域活性化の一環としても注目されています。地方の過疎化が進む中で、外部からの人材や子どもの受け入れを通じて、地域に新しい風を呼び込むことが期待されているのです。
離島留学や漁村留学との違い
山村留学と聞くと、「離島留学や漁村留学と何が違うのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
離島留学は、島外の小中学生や高校生が豊かな自然環境や文化・伝統が残る離島で暮らし、勉学に励む留学スタイルです。一方、漁村留学は漁村という環境で漁業や海洋文化に触れる機会が多い留学スタイルといえます。このように、留学先の環境がそれぞれ異なります。
- 離島留学:海に囲まれた島という特殊な環境での生活
- 漁村留学:漁村で漁業や海洋文化に触れる機会が多い
- 山村留学:山間部で農業や林業、伝統文化に触れる機会が多い
いずれも自然豊かな環境で生活し、地域の人々との交流を通じて人間的な成長を促すことが目的です。
山村留学の歴史
山村留学は、1976(昭和51)年に長野県八坂村(現・大町市八坂)において「公益財団法人育てる会」の教育実践活動として、日本で初めてシステム化された教育活動です。都市化が進むにつれて自然との関わりが減少したことで、「子どもの自然体験を増やしたい」「豊かな自然の中で子どもたちの豊かな感性や創造性を伸ばしたい」という考え方が増えたのです。
当初は、長期休暇中に自然体験活動を実施していましたが、保護者から「一年間、地域に住んで学校に通わせたい」という要望を受け、一年間の山村留学が誕生しました。
どんな地域が受け入れているのか
山村留学を受け入れている地域は、北海道や長野県、高知県や鹿児島県など、日本各地に広がっています。
これらの地域は、豊かな自然環境に恵まれているだけでなく、地域全体で子どもを支える体制が整っていることが特徴です。住民同士のつながりが強く、子どもたちにとって安心できる環境が整えられています。
山村留学で得られる5つのメリット

山村留学の魅力を深掘りするために、山村留学で得られるメリットを5つ紹介します。
1.豊かな自然体験
山村留学では、都市部では味わえない豊かな自然体験ができます。例えば、山や川での遊び、田植えや稲刈りなどの農業体験、星空観察など、自然の力強さや美しさに触れられる機会も大きな魅力です。
2.集団生活を通しての成長
ホームステイ生や寮生活など、共同生活を通して、協調性を育むことも期待できます。子どもたちは、自分たちで身の回りのことを行ったり、仲間と協力して生活したりする中で、社会性を身につけ、責任感や自立心も養えます。
3.地域の人々との交流
山村留学を受け入れる地域の人々は、子どもたちを受け入れ、あたたかく見守ってくれます。地域の人々との交流は、あたたかい人間関係を築き、思いやりの心を育むことにもつながります。さまざまな世代の人と関わることで、地域社会への理解が深まり、豊かな人間性を育むことも期待できるでしょう。
4.個に合わせた教育
山村留学先の学校は、都市部の学校に比べて少人数です。教師の目が行き届きやすいため、個に応じたきめ細かな指導を受けることが可能です。また自然体験や地域交流など、体験学習が充実しているため、子どもたちの五感が刺激されます。これらの活動は、個性や才能を伸ばすことにもつながります。
5.地域への貢献
子どもたちを受け入れることで、地域に活気が生まれ、地域経済の活性化にもつながります。
山村留学で地域の文化や伝統を学んだ子どもや家族の中に、「この地域が好きだ」「この地域のために自分も何かしたい」「この地域に住みたい」など、地域の担い手が生まれるかもしれません。山村留学は、過疎化が進む山村地域にとって、新たな活力を生み出すことが期待できるでしょう。
山村留学の費用と支援制度

山村留学の費用は、団体や生活形態によって異なりますが、主に、宿泊費、食費や生活費、教材費や授業料、活動費や交通費用などがかかります。
ホームステイ、寮など生活する場所によって異なりますが、NPO法人全国山村留学協会によると、月謝はおおよそ40,000〜90,000円の範囲といわれています。寮の場合は施設の維持や指導員の人件費などの経費が増えるため、費用が高くなる傾向にあります。しかし、寮に専任指導員がいる場合は、休日などの活動が充実するメリットもあるでしょう。
参考:Q&A | 山村留学とは | NPO法人 全国山村留学協会
月謝とは別に、子ども個人にかかる費用(散髪、通院、文具の購入など)、学校関係費用(PTA会費、給食費など)なども必要です。費用を検討する際は「子どもにどんな体験をさせたいか」を明確にした上で、山村留学での体験に見合った費用かどうかを、しっかりと吟味する必要があります。
山村留学の3大デメリット
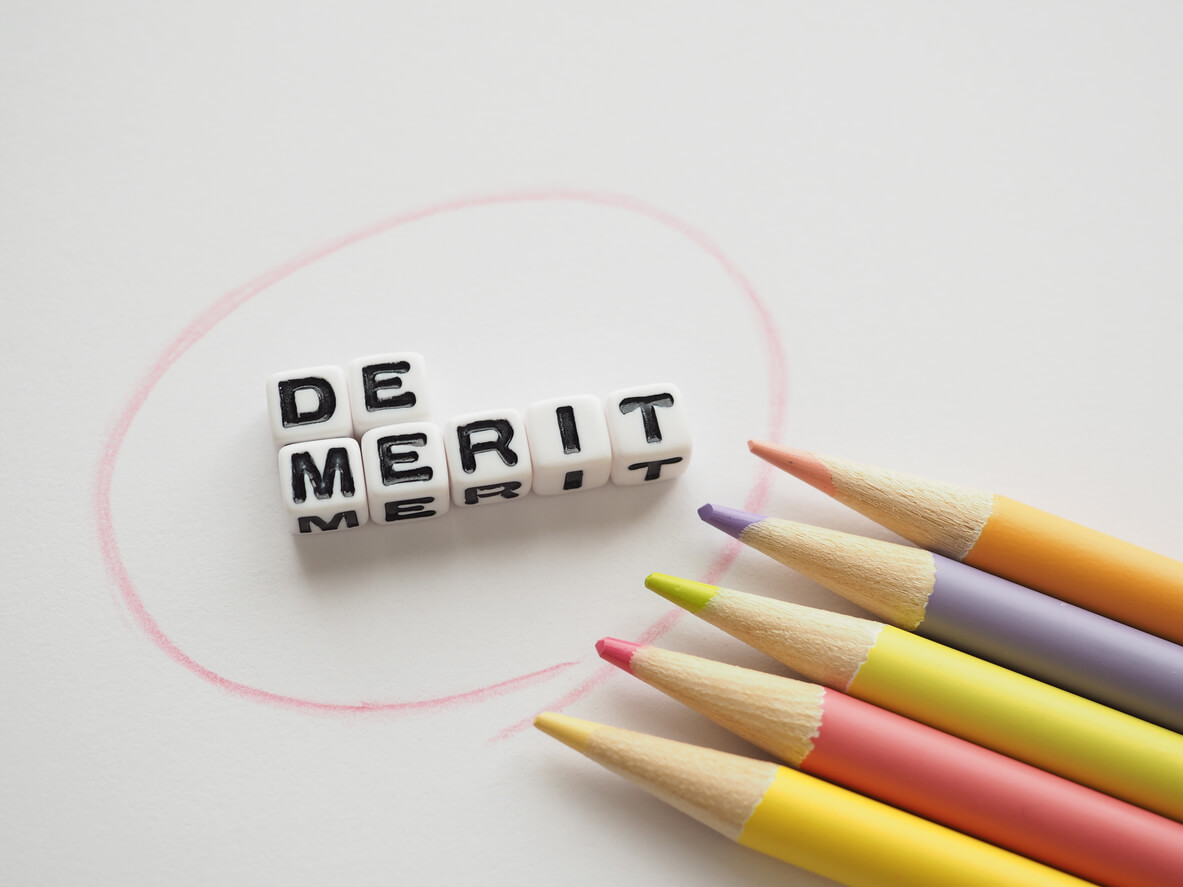
山村留学は、メリットだけでなく、デメリットも存在します。山村留学を検討する際には、メリットとデメリットをよく理解し、子どもにとって本当に良い選択かどうか、しっかりと見極めることが大切です。
①費用の負担が大きい
山村留学は、プログラムの費用や送り出しにかかる時間の負担が大きいと感じる方もいます。しかし、これらの負担は支援制度の活用やスケジュールの工夫で軽減できます。山村留学の費用を抑えるためには、自治体や国が提供する補助金や奨学金制度を活用することが有効です。自治体の中には「地域創生」や「子育て支援」を目的として、費用の一部を支援しています。
例えば、鹿児島県の湧水町では、留学生が豊かな自然の中でのびのびと小学校生活を送り、保護者も安心して子どもを留学させられるように補助金を交付しています。
- 里親・親戚留学生の場合は1人につき、月額40,000円
- 親子・家族留学生の場合は、留学生1人目は月額40,000円、2人目以降は月額10,000円
ただし、申請には、申請書などの書類の提出が必要なことが多いため、事前に確認しておくことが大切です。補助金制度の有無や内容は、お住まいの自治体や受け入れ団体の自治体に問い合わせてみてください。
②環境の変化によるストレス
山村地域は、自然豊かで住みやすい環境が整っています。しかし、都市部から自然豊かな山村地域に移住することは、生活環境の大きな変化を伴います。慣れない環境での生活は、子どもにとって大きなストレスとなる可能性もあるのです。また、子どもが親元を離れることで、親子双方に心理的な負担が生じることがあります。
少しでも心理的な不安を軽減させるためには、留学前に、親子で実際に山村留学地を訪れたり、体験留学に参加したりすることがおすすめです。子どもは新しい環境に事前に触れられ、不安やストレスを軽減できます。
③地域住民とのトラブル
山村留学では、受け入れ地域や家庭との相性が合わない場合、子どもや親にとってストレスになることがあります。都市部と山村地域では、生活習慣や文化が異なるため、地域の人々との間にトラブルが生じることも考えられます。これらの問題を防ぐには、事前のリサーチや十分な話し合いが必要です。
例えば、受け入れ家庭や地域の特徴を事前に調べたり、プログラム担当者と具体的な希望や懸念を相談したりすることで、ミスマッチを減らせるでしょう。山村留学先の生活リズムで過ごす練習をしたり、郷土料理を家で作って食べてみたりするなど、リハーサルをしておくと、環境になじみやすくなります。
初めての山村留学!成功のための5つのステップ

山村留学は、子どもにとってかけがえのない成長体験となる貴重な機会です。しかし、初めての山村留学となると、期待と同時に不安も抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。そこで、山村留学を成功させるための5つのステップを紹介します。
ステップ1:山村留学の目的を明確にする
山村留学には、自然体験・集団生活・地域交流など、さまざまな目的があります。まず、「どのような目的で山村留学をさせたいのか」を家族でよく話し合い、明確にすることが重要です。
例えば、「自然の中で体力向上を図りたい」「協調性を身に付けたい」「異文化に触れて視野を広げたい」など、具体的な目標を設定しましょう。漠然とした目的ではなく、具体的な目標を設定することで、留学生活での方針が定まり、モチベーション維持にもつながります。
ステップ2:情報収集とプログラム選び
山村留学を実施している団体は全国に数多く存在し、それぞれに特色があります。子どもの目的や性格に合ったプログラムを選ぶことが重要です。
情報収集の方法は、以下のものがあります。
- 各自治体の公式サイト
- NPO法人全国山村留学協会
- 山村留学体験談など
プログラム選びのポイントは、以下の点を考慮しましょう。
- 対象年齢:山村留学は義務教育期間の子どもが対象だが、受け入れ団体によって対象年齢が異なる
- 募集人員:受け入れ人数が少ない場合もある
- 生活形態:ホームステイ・寮・親子留学など、さまざまな生活形態がある
- 費用:プログラム費用・生活費・学校関係費用など、さまざまな費用がかかる
- 指導員の考え方:指導員の考え方や教育方針も、山村留学の成功に大きく影響する。体験留学などで、指導員と直接会って話をする機会を設けるとよい
また、山村地域の学校は、都市部の学校に比べて小規模な学校が多く、選択できる科目や部活動が少ない場合があります。事前にしっかり確認することをおすすめします。
ステップ3:事前準備と心構え
山村留学では、通常の生活では使わない道具や用品が必要になることがあります。特に山村地域は都市部に比べて気温が低く、冬は特に寒さが厳しい地域もあるため、防寒具や長靴などの準備が必要です。
一方で、スマホやゲーム機、マンガの持ち込みが禁止されている留学地が多いのも特徴です。事前に受け入れ団体に確認しておきましょう。
また、山村留学では、自分のことは自分でするように指導されます。身の回りのことを自分でできるよう、練習することが重要です。さらにスムーズに地域の方と交流できるように日頃から、近所の人に挨拶をしたり、地域の行事に参加したりするなど、積極的に交流しましょう。
ステップ4:家族のサポート体制
山村留学は、家族全体でのサポート体制が重要です。山村留学中は、子どもがホームシックになることもあります。電話や手紙などで、こまめに連絡を取り、子どもの気持ちを聞き取り、励ましましょう。
各地域には、最低限のルールがあります。保護者もルールを守り、現地を混乱させないよう、注意が必要です。
ステップ5:山村留学後のフォロー
山村留学で得た経験を、今後の成長につなげるためには、山村留学後のフォローも大切です。山村留学で経験したことを家族で共有したり、写真や日記などに残したりすることで、子どもは自分の成長や努力を再確認できます。
山村留学でできた友人や地域の人々とのつながりを大切にし、交流を続けることは、子どもの一生の財産となるでしょう。
山村留学が生み出す新しい学びと地域の活性化

小学生や中学生で親元を離れるのは早いのではないかと思う方もいるかもしれません。しかし、山村留学は、子どもにとって自然の中で自分らしく成長できる特別な体験であり、親にとっても新しい発見の場となります。
まずは情報収集から始め、子どもと一緒に留学の目的や希望を話し合うことが重要です。事前準備を進めることで、トラブルを回避し、山村留学が家族全員にとって実りある経験となるでしょう。
また、過疎化の可能性がある地域の活性化の役割にもなっています。山村留学は、子どもだけではなく、地域の将来も豊かにする教育活動として、今後さらに注目されるのではないでしょうか。
参照:文部科学省|就学校の指定・区域外就学の活用状況調査について
参照:総務省|山村留学等の学びを中心とした関係人口(ファン)づくり事業
参照:国土交通省|離島の学校に通いませんか?ー令和6年度離島留学生を募集しています
参照:国土交通省|離島振興法
参照:シマ育|離島留学とは
参照:公益財団法人 育てる会
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











