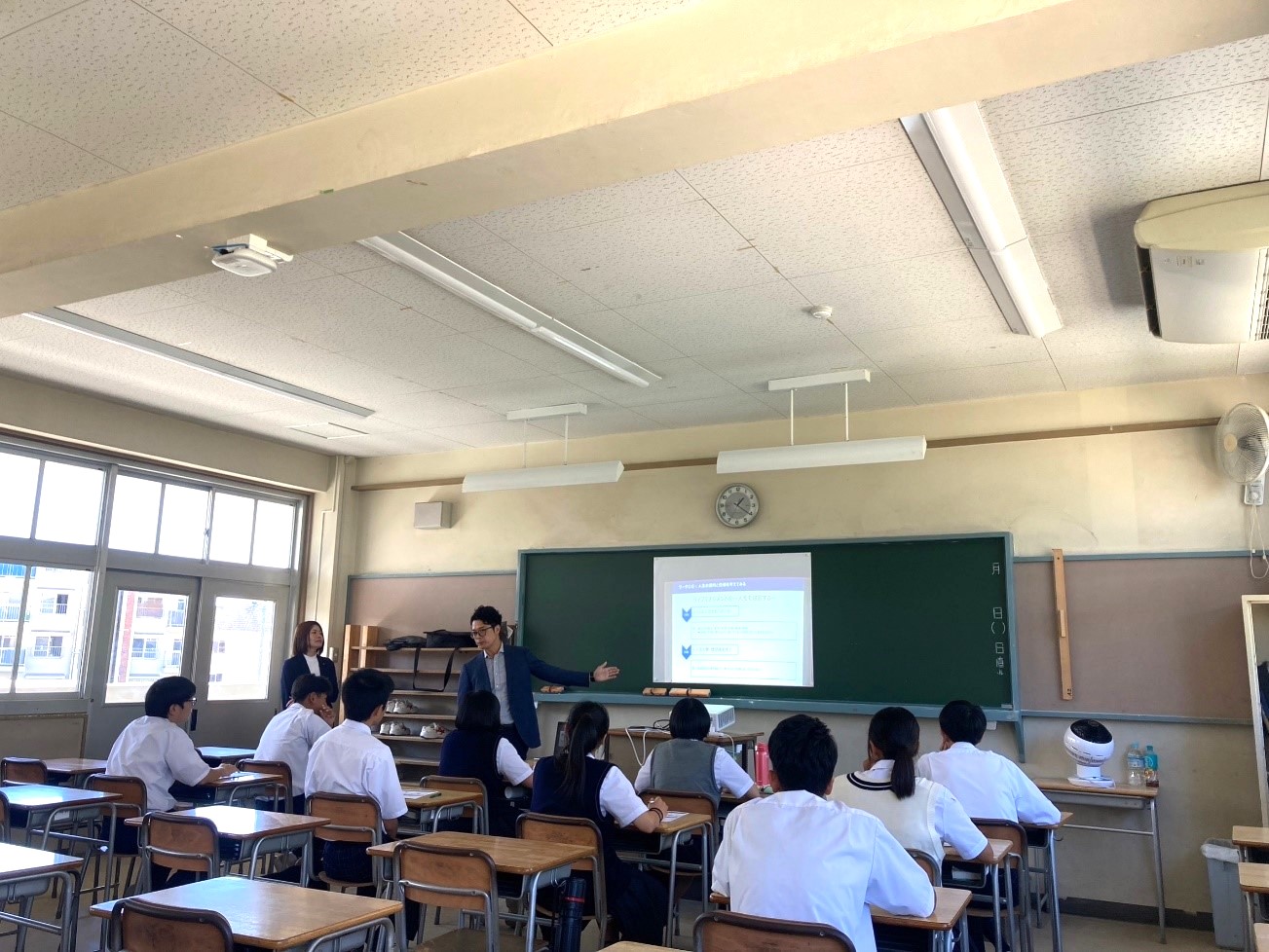ダイバーシティとは?簡単に解説!企業での必要性や成功事例も紹介

「多様性」を意味する「ダイバーシティ(Diversity)」という言葉が一般的になりつつあります。ビジネスシーンでも、見聞きする機会が増えてきました。ダイバーシティを企業経営に取り入れる「ダイバーシティ経営」は、政府により推進されています。
そこで本記事では、今さら聞けない「ダイバーシティとは何か?」を簡単に分かりやすく解説し、ダイバーシティ経営のメリットや必要性を、企業事例を交えながら紹介します。一緒に使われることの多い「インクルージョン」や「D&I」にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
ダイバーシティとは?

冒頭で触れたとおり、ダイバーシティ(Diversity)とは「多様性」を意味する言葉です。「人にはそれぞれ違った特徴や価値観があり、その違いを認めて尊重しよう」との考え方です。
ダイバーシティには性別や年齢はもちろん、人種・障がいの有無・働き方や雇用形態の違い、考え方の違いなども含まれます。多様性を受け入れ、さまざまな人がそれぞれの個性や力を発揮できることが社会全体の成長にもつながると考えられています。
ダイバーシティの種類
ダイバーシティは大きく分けて、表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティの2つがあります。
以下に、表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティの一例を挙げてみます。
| 表層的ダイバーシティ | 深層的ダイバーシティ | |
|---|---|---|
| 特徴 |
|
見た目では判別しにくい |
| 具体例 | 性別・年齢・国籍・障がいの有無・容姿・人種 | 性格・価値観・宗教・性的志向・スキル・職務経験・趣味・考え方・働き方・雇用形態 |
上記はほんの一例でしかなく、実際にはもっと多くの属性があります。ダイバーシティを考えるうえで注意しなければならないのは、アンコンシャス・バイアスです。日本語では「無意識の思い込み」と表現されます。
例えば、「障害のある人は普通に働くのが難しいはず」「お茶出しは女性の仕事」「外国人は時間にだらしない」「パートは働く意欲が低い」のような偏見や思い込みは、相手を傷つける可能性があります。自分の常識を疑い、多様な考えを受け入れる姿勢が大切です。
参考:内閣府|共同参画
なぜ今ダイバーシティが重要なのか

日本では、ダイバーシティがこうも重要視されるのはなぜでしょうか。その理由には、労働人口の減少やグローバル化、価値観の多様化などが挙げられます。
こうした変化に対応するためには多様な人を受け入れ、それぞれの力を最大限発揮してもらうことが必要です。次項で詳しく見てみましょう。
労働人口の減少と高齢化
日本では、少子高齢化の影響により労働人口が減ってきています。内閣府の調査によると、生産年齢人口(15〜64歳)は減少の一途をたどっており、2065年には約4,500万人となる見通しです。これは2020年と比べて、約2,900万人の減少となります。
さらに、2065年には老年人口(65歳以上)の割合が約4割に達する一方で、生産年齢人口の割合は約5割に低下する見通しです。
このままでは働く人が足りなくなり、経済や生活に影響を及ぼします。そこで、定年の引き上げや時短勤務・在宅勤務の導入、国籍や性別に関係なく働ける環境作りなど、働く人を増やすための取り組みが必要です。
グローバル化と企業競争力の関係
グローバル化が進む昨今、企業は日本だけでなく海外を意識したビジネスを行う必要性が出てきました。
リテール業であれば、英語・中国語・韓国語など外国語を話せる人材の雇用により、海外顧客の取りこぼしを防げます。海外進出を目指しているのであれば、現地の文化や風習を理解している人材の雇用により、現地人のニーズに合った商品やサービスを提供できます。
多様な人材を受け入れることで、企業は海外でも競争に勝てる力を得られるでしょう。
消費者ニーズや価値観の多様化
最近は人々の好みや考え方が多様化し、誰もが同じものを求める時代ではなくなってきました。例えば、ファッション・LGBTQ+に始まり、宗教上の理由や倫理的観点から食事を選ぶ人、型にとらわれない家族の形など、実にさまざまです。
企業は、どのような人にも合う商品や、使いやすいサービスを考える必要があります。
例えば、カレーをひとつ取ってみても、肉や動物性由来の材料を一切使用しないベジタリアン向け・ヴィーガン向けのものから、グルテンアレルギーの人でも食べられるもの、何も制限のない人が満足できるものなど、多様なパターンを考慮することでより多くの人に選ばれる企業になります。
多様な価値観に対応する力は、これからの時代に欠かせないものといえるでしょう。
インクルージョンとは?多様性を活かす考え方

ダイバーシティと一緒によく聞かれる言葉に「インクルージョン」があります。多様な人々が力を発揮できるためには、インクルージョンの考え方が欠かせません。
インクルージョン(Inclusion)は直訳すると「包括」ですが、具体的に何のことか分かりにくいでしょう。そこで、ダイバーシティとセットで使われることの多いインクルージョンを解説します。
ダイバーシティとインクルージョンの違い
ダイバーシティとインクルージョンは、似ているようで役割が違います。
『三省堂国語辞典(2022年の第八版)』では、インクルージョンを「いろいろな人が個性・特徴を認めあい、いっしょに活動すること」と定義しています。
簡単にいうと「いろいろな人がいる(=ダイバーシティ)」だけではなく、「いろいろな人がお互いを認めあい、ともに活躍できるようにする」のがインクルージョンです。
例えば、職場にさまざまな国籍の人がいるとしましょう。この状態はダイバーシティです。しかし、言語や宗教上の問題からプロジェクトを外されたり、会議で自由に発言できなかったりするとしたら、インクルージョンがあるとはいえません。
これではダイバーシティがあっても意味がありません。インクルージョンは誰もが認められ、受け入れられる環境を作る考え方です。
ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)とは
前述のとおり、ダイバーシティとインクルージョンはセットで使われることが多いため、「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」と呼ばれます。ダイバーシティ&インクルージョンは「多様な人を受け入れるだけでなく、多様な人たちが活躍できるようにする」までを含めた概念です。
ダイバーシティ&インクルージョンは、第 32 回オリンピック(2020年東京開催)の基本コンセプトでした。
ダイバーシティ経営のメリットと必要性

ダイバーシティを経営に取り入れる企業が増えてきました。経済産業省の定義によると、ダイバーシティ経営とは「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」のことです。
ダイバーシティ経営は、企業の成長にも良い影響を与えると期待される経営手法です。ここからは、企業がダイバーシティ経営を進めるメリットと必要性を具体的に解説します。
多様・優秀な人材の獲得
ダイバーシティ経営を行う企業は、性別・国籍・障がいの有無・時短勤務希望の人材・出社困難な遠方に住む人材など、幅広い人材を採用しています。これは、採用競争の激しい現在において大きな強みです。
特にミレニアル世代は、企業の「多様性や受容性の方針」を重要視して就職先を選択する傾向があり、中でも女性はこの傾向が顕著とのデータも出ています。
人材の多様性が増すことは、生産性の向上や人手不足の解消など、企業にとっても大きなメリットがあります。
イノベーションの創出
新しいアイデアを生み出すためには、多様な人材の異なる考え方や価値観が必要です。多様な視点がぶつかり合うことで、より良い商品やサービスの開発に貢献するのはもちろん、新規事業の立ち上げにつながることもあるでしょう。
ダイバーシティ経営に取り組む企業は柔軟な働き方や意見を出しやすい社風が整っていることもあり、売上高や生産性が高く、業務効率化にもつながっています。
対外評価の向上とリスクマネジメントの強化
ダイバーシティ経営に積極的な企業は、前述したように優秀な人材を獲得しやすくなります。多様性に配慮した組織作りは、企業イメージやブランドイメージの向上にも貢献するでしょう。
さらに、さまざまな視点を持つ人材が集まる組織では、複数の視点からリスクマネジメントを実施できます。結果として潜在リスクを事前に察知し、適切な対処ができる可能性が高まります。
ダイバーシティ経営に取り組む企業事例

ダイバーシティ経営に取り組む企業の事例を見てみましょう。実際に成果をあげている企業の事例を知ることで、自社におけるダイバーシティ経営の重要性と実現の可能性を検討してみてください。
大橋運輸
大橋運輸は愛知県の運送会社です。人材確保が難しいとされる運輸業で、女性従業員が2割以上在籍するほか、外国籍・LGBTQ・障がいのある従業員も活躍しています。
あえて短時間かつ柔軟な勤務形態で人材を募集し、優秀な人材を確保したり、短時間勤務の女性従業員を管理職へ登用したりするなど、多様な人材が活躍できる工夫をしています。
意見が通りやすい環境整備にも励んでおり、社長へ直接意見を挙げられる「社長直通メール」は、主力となる新規事業の立ち上げにも貢献しました。
こうした取り組みが評価され、2020年には中小企業として初めて経済産業省の「新・ダイバーシティ経営100選プライム」に選定、ダイバーシティ経営のロールモデルとして注目されています。
熊谷組
建設業界で活躍する熊谷組は、女性の活躍を推進するさまざまな取り組みを行っており、外部の評価団体からも女性が活躍できる職場として評価を受けています。
具体的には、えるぼし認定取得、なでしこ銘柄に選定、PRIDE指標ゴールド受賞、くるみん認定、新・ダイバーシティ経営企業100選に選定などです。ダイバーシティの推進後9年間で、女性管理職数は11名から88名にも増加しました。
建設業では珍しく、フレックス勤務・時差出勤・テレワーク制度の整備や、ライフステージの変化に応じて男女を問わず従業員を柔軟にサポートする、さまざまな制度を取りそろえています。特筆すべきは「ダイバーシティパトロール」で、ダイバーシティ推進担当者が実際に建設現場を訪問し、取り組み状況を確認・ヒアリング、要望に応じて改善する取り組みです。
日立ハイテク
グローバルに展開する日立ハイテクでは、性別・年齢・国籍・人種・障がい・性格・価値観・性的指向・キャリアなど、社員がもつ違いを「その人がもつ個性」と捉え、力を十分に発揮できる仕組みの充実に積極的に取り組んでいます。
2023年度入社の新入社員のうち外国籍従業員比率は11.9%です。建屋内に祈祷室を設置する、カフェテリアでハラール対応メニューの提供を行うなど、宗教にも配慮した体制をとっています。
さらにコアタイムなしのフレックスタイム制、在宅勤務・サテライトオフィス勤務・ロケーションフリーワークの対象者を全従業員に拡大、男性育休取得率100%を目指した「全力育児応援プロジェクト」の実施など、すべての従業員が働きやすい環境を用意しています。
J-Winダイバーシティ・アワード、えるぼし認定取得、PRIDE指標ゴールド受賞、プラチナくるみん認定、新・ダイバーシティ経営企業100選に選定など、外部からも高く評価されています。
カンロ
創立100年を超える老舗製菓企業のカンロは、2018年に「ダイバーシティ委員会」と「ダイバーシティ推進室」を立ち上げ、全社を挙げてダイバーシティ経営に取り組んでいます。
2018年に座席のフリーアドレス化と服装自由化を実施、2019年にフレックスタイム制度のコアタイム短縮、毎週水曜日のリフレッシュデー、コロナ禍以前の2020年1月にはすでにテレワーク制度を導入するなど、家庭と仕事の両立や働く場所と時間の選択肢を増やしました。
また、短時間勤務中の女性従業員を初めてリーダーに起用したことで、従来のキャンディ市場にはなかった「親子」をターゲットとした新商品の開発に至りました。同商品の売上実績は計画比約140%を達成しています。屋内ハーブ農園「カンロファーム」では、定年退職した従業員や障害のある方が活躍中です。
こうしたさまざまな取り組みにより、令和2年度の新・ダイバーシティ経営企業100選に選出され、ベストプラクティス集に掲載されました。
参考:経済産業省|令和2年度ダイバーシティ経営企業100選 ベストプラクティス集
まとめ

ダイバーシティとは、性別・年齢・人種・障がいの有無・雇用形態などに関係なく、多様な人が尊重され共存する考え方です。そして、それぞれの違いを受け入れて生かす「インクルージョン」も、ダイバーシティと同様に重要な概念です。
労働人口の減少やグローバル化、価値観の多様化が進む中で、ダイバーシティは企業の持続的な成長に欠かせません。多様な人を受け入れ、働きやすい環境を作ることで、人材不足の解消だけでなく、イノベーションの創出や外部からの評価にもつながります。
中小企業・大企業を問わず、ダイバーシティは始められます。まずは自社の従業員一人ひとりの小さな違いや価値観を尊重するところから始めましょう。「どのような制度があったら働きやすいか?」「どうしたら一人ひとりが力を発揮できるか?」の対話を重ね、一歩ずつ進めていくことが大切です。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!