ペロブスカイト太陽電池のデメリットとは?注目企業と実用化時期を解説

ペロブスカイト太陽電池と聞いて「従来の太陽電池と何が違うのか」「いつから実用化されるのか」と感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ペロブスカイト太陽電池のしくみやデメリット、そして国内外の企業事例や市場の最新動向をわかりやすく解説します。
読むことで、次世代エネルギーの最前線を理解し、自社の技術やビジネスにどんな可能性があるのかを見つけるヒントが得られます。
ペロブスカイト太陽電池とは
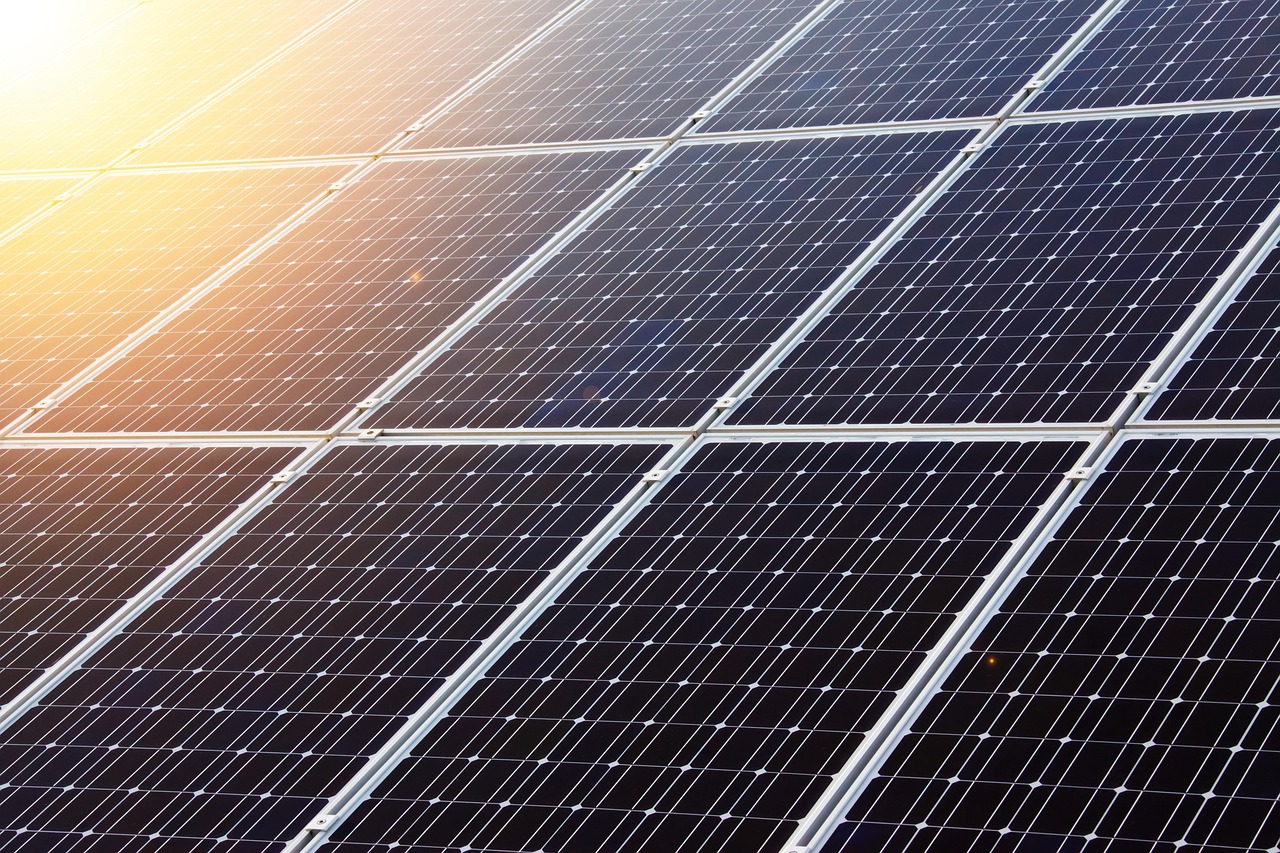
ペロブスカイト太陽電池とは、太陽の光を電気に変える新しいタイプの薄型太陽電池です。2009年に日本の研究者らによって発明されました。
ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造を持つ化合物を発電層に用いています。この結晶は光吸収率が高く、電子をスムーズに動かす性質を持っています。少ない光でも効率よく発電できるのが特徴です。
光を電気に変えるしくみ
ペロブスカイト太陽電池は、太陽光を吸収すると、内部でマイナスの電荷を持つ電子とプラスの電荷を持つ正孔(ホール)が大量に生成され、電気を生み出します。
電気を運ぶ部品のはたらき
ペロブスカイト太陽電池は、いくつかの層が重なっているのが特徴です。
真ん中のペロブスカイト層が光を吸収して電子を作り、上下の電子輸送層とホール輸送層がそれぞれ電子とホールを運びます。外側の電極が電気を外へ送り出し、発電効率を高めるしくみになっています。
発電効率を上げるための工夫
ペロブスカイト太陽電池の性能を上げるには、光をできるだけ多く吸収し、電子をスムーズに動かす工夫が欠かせません。
たとえば、材料の配合を変えて光を吸収しやすくする研究が進められています。ペロブスカイト層を保護する薄い膜を重ねることで、湿気や熱から守り、長く使えるようにする工夫もあります。
参照:経済産業省|日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?
参照:株式会社倉元製作所|ペロブスカイト
参照:ACS Publication|Influence of the Electron Transport Layer on the Performance of Perovskite Solar Cells under Low Illuminance Conditions
参照:産総研マガジン|ペロブスカイト太陽電池とは?
参照:The Royal Society of Chemistry|Current status of electron transport layers in perovskite solar cells: materials and properties
参照:MDPI|Perovskite Solar Cells: A Review of the Latest Advances in Materials, Fabrication Techniques, and Stability Enhancement Strategies
参照:国立研究開発法人科学技術振興機構|ペロブスカイト型太陽電池の開発
参照:国立研究開発法人科学技術振興機構|ペロブスカイト太陽電池で目指すグリーンエネルギー社会の実現
ペロブスカイト太陽電池の特徴

ここでは、ペロブスカイト太陽電池の構造や種類、製造方法など、詳しく解説します。
ペロブスカイト太陽電池の構造と材料
ペロブスカイト太陽電池は、「ペロブスカイト構造」と呼ばれる特別な形の結晶を使って作られています。高性能な鉛タイプが主流ですが、環境にやさしいスズを使う鉛フリー材料の研究も進んでいます。
ペロブスカイト太陽電池の種類
ペロブスカイト太陽電池は、「フィルム型」「ガラス型」「タンデム型(ガラス)」に分けられます。
フィルム型は、薄くて軽く曲げられるのが特徴です。製造プロセスに日本の塗布技術が活用されています。
ガラス型は、従来のガラス建材と一体化できるのが特徴です。フィルム型と比べて耐水性が高く、耐久性を確保しやすいメリットがあります。
タンデム型(ガラス)は、一般的に普及しているシリコン太陽電池の置換えとして期待されています。ただし、開発の進捗は、フィルム型やガラス型より遅れているのが懸念点です。
ペロブスカイト太陽電池の製造方式
ペロブスカイト太陽電池の製造には、印刷や塗装といった簡単な方法を使えるのが大きな特徴です。
一般的に、液体状の原料をガラスやフィルムの上に薄く広げて乾かす方法や、連続的に塗っていくロール・ツー・ロール(R2R)方式が使われます。大きな装置や高温処理が不要で、低コストで生産できるのが強みです。
参照:経済産業省|次世代型太陽電池戦略
参照:経済産業省|グリーンイノベーション基金事業「次世代型太陽電池の開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画
従来のものとの違いから考えるメリット

ペロブスカイト太陽電池は、薄くて軽いことに加えて発電効率が高いのが特徴ですが、他にも期待されている要素がいくつかあります。
ここでは、ペロブスカイト太陽電池のメリットについて、従来のものと比べながら解説します。
製造コストが低く、国内材料で調達可能
ペロブスカイト太陽電池は、製造工程が少ないため、製造コストを大幅に下げられます。
ペロブスカイト太陽電池の主な原料であるヨウ素は、日本でも手に入りやすく、海外からの輸入に頼らずに作れる点が強みです。国内での生産が増えれば、エネルギーの安定供給やコスト削減にも寄与します。
弱光でも発電できる
ペロブスカイトは、光を吸収しやすい結晶構造を持っているため、少ない光で電気を作ることが可能です。従来のシリコン太陽電池では難しかった、曇りの日や室内の明かりでも発電できます。
屋根・壁・車など、自由なデザインに対応
ペロブスカイト太陽電池は、建物のガラスや壁に溶け込むように設置でき、見た目を損なわずに発電できます。車のボディや曲面にも貼り付けられるため、デザイン性と機能性を両立したエネルギー利用が可能です。
環境負荷が低い
ペロブスカイト太陽電池は、従来の太陽電池に比べて少ない材料で作れるため、製造時に必要な消費エネルギーを軽減できます。
室内光でも発電できるため、より多くの場所で再生可能エネルギーを活用することが可能です。カーボンニュートラル社会を実現するために不可欠な手段として注目されています。
地域の新しい産業づくりにつながる
ペロブスカイト太陽電池は、従来の太陽電池では設置が困難であった場所にも導入できるため、地域社会との共生が期待されています。
日本政府は、ペロブスカイト太陽電池の導入拡大に向け、必要なスキルを有する人材育成の強化を検討中です。地方の中小企業が部品製造や建材加工などに参入すれば、事業拡大や雇用創出も期待できます。
再生可能エネルギーの地産地消や、地方の活性化にも寄与するといえます。
参照:経済産業省|日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?
参照:国立研究開発法人科学技術振興機構|ペロブスカイト太陽電池で目指すグリーンエネルギー社会の実現
参照:経済産業省|次世代型太陽電池戦略
関連記事:日本企業のカーボンニュートラルへの取り組み|メリットや方法も解説
ペロブスカイト太陽電池のデメリット

ここでは、ペロブスカイト太陽電池の導入・拡大に向けて解決すべき課題について解説します。
耐久性
ペロブスカイト太陽電池は、湿気や熱に弱く、長時間の使用で性能が下がりやすいため、従来の太陽電池に比べて寿命が短いことが課題です。そのため、屋外での使用に耐えるための研究が進められています。
鉛の安全性
ペロブスカイト太陽電池の代表的な組成には鉛が含まれており、安全性や環境への影響も懸念されています。
現在は、鉛を使わない技術開発が進行中です。京都大学では、高機能な鉛フリー型太陽電池の開発に成功しました。
大面積化の難しさ
小さいサイズの場合は性能が高いものの、サイズが大きくなると性能にばらつきが出やすいため、大面積化の難しさが課題です。
高い発電効率を維持できるように、製造時に原材料を大面積のフィルムに均一に塗布する技術が求められています。
量産技術の壁
ペロブスカイトの導入・拡大には、安定して大量に生産する技術が必要です。
積水化学工業は、ロール・ツー・ロール方式の製造による量産化技術の開発に注力しています。複数のドラム・ロールを使い、30cm幅の製品を搬送しながら印刷や塗装などの工程を連続的に行う生産方式を実現しました。今後は、2025年の事業化に向けて、1m幅での製造技術の確立を目指しています。
参照:国立研究開発法人科学技術振興機構|ペロブスカイト太陽電池で目指すグリーンエネルギー社会の実現
参照:経済産業省|日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(後編)~早期の社会実装を目指した取り組み
本格的な実用化はいつからか
ペロブスカイト太陽電池は、2030年ごろの実用化を目指しており、日本政府も実用化に向けた取り組みを後押ししています。
たとえば、2兆円規模の「グリーンイノベーション(GI)基金」が創設され、その中の「次世代型太陽電池の開発プロジェクト」には、約498億円の予算が割り当てられました。
この支援により、IoT機器や建物用への展開も可能な太陽電池や、ペロブスカイト材料を均一に塗布するスプレー工法の技術など、複数の企業や大学が連携して実用化に向けた研究開発が進められています。
参照:経済産業省|日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(後編)~早期の社会実装を目指した取り組み
市場規模予測と競合動向
世界では、2035年までに1兆円規模の市場に達すると見込まれています。
日本だけではなく、中国やイギリス、ポーランドなど海外でも、量産化に向けた開発が急速に進められています。ただし、日本が世界市場で生き残るためには、2030年よりも早い段階での社会実装が必要です。
今後は、競争が激化する状況が予想されるため、2023年8月には「産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会グリーン電力の普及促進等分野ワーキンググループ」にて、早期の社会実装を実現する、開発事業の予算を150億円増額し、合計648億円とすることが決定されました。
日本でペロブスカイト太陽電池の実用化を確立するためには、量産技術や安定した生産体制を早急に整備することが不可欠です。
参照:メガソーラービジネスplus|ペロブスカイト太陽電池、2020年代半ば量産、35年に1兆円規模
参照:経済産業省|日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(後編)~早期の社会実装を目指した取り組み
国内外の企業事例

ここでは、ペロブスカイトの発展を支えている国内外の企業事例について紹介します。
エネコートテクノロジーズ
エネコートテクノロジーズは、京都大学発のスタートアップ企業です。
共同創業者であり最高技術顧問の若宮教授の研究チームは、環境負荷の低いスズを用いたペロブスカイト太陽電池の製造に成功しました。
2025年10月21日より、JR九州および日揮と共同で、博多駅第2ホーム屋根上にてフィルム型ペロブスカイト太陽電池の発電実証実験を開始しました。駅ホームの屋根上での実証は、国内初の取り組みとなります。
参照:株式会社エネコートテクノロジーズ|NEWS & TOPICS
Opteria(オプテリア)
オプテリアは、ガスバリアフィルムを開発・製造しています。ガスバリアフィルムは、通常のフィルムよりも水蒸気や酸素を通しにくく、丸めたり折り曲げたりすることも可能です。
ガスバリアフィルムを使用することで、課題となっている耐久性の向上が期待されています。
Peccell Technologies(ペクセル・テクノロジーズ)
ペクセル・テクノロジーズは、桐蔭横浜大学が立ち上げたベンチャー企業です。光電気化学を専門とし、事業を展開しています。
「自動スピンコータ」や「インクジェット印刷機」といった、性能のばらつきが少ないペロブスカイト太陽電池を製作できる自動成膜装置を販売しています。
参照:ペクセル・テクノロジーズ株式会社|会社概要
参照:ペクセル・テクノロジーズ株式会社
倉元製作所
倉元製作所は、ペロブスカイト太陽電池の事業化に取り組んでいる企業です。
装置メーカーや材料メーカーとのタイアップを通じて、ペロブスカイト太陽電池の量産化に必要な材料成膜、材料塗布、パターニング、封止の生産技術の確立に尽力しています。
東京化成工業(TCI)
東京化成工業は、ペロブスカイト太陽電池の製造に不可欠な材料の製造・販売を担っている企業です。
高純度なペロブスカイト原料を豊富なラインナップで提供し、研究開発をバックアップしています。
参照:国立研究開発法人科学技術振興機構|ペロブスカイト太陽電池で目指すグリーンエネルギー社会の実現
参照:東京化成工業株式会社|有機無機ペロブスカイト原料
Saule Technologies(サウレ・テクノロジーズ)
ポーランドのサウレ・テクノロジーズは、ペロブスカイト太陽電池を柔軟な薄膜シートに塗布する技術を事業化するために、バレンシア大学のオルガ・マリンキエヴィツ氏によって設立されました。
2021年には世界で初めて、ペロブスカイト太陽電池セルの製造ラインを完成させました。
日本の旅行会社HISは、2015年よりサウレ・テクノロジーズに出資しており、2024年12月からは東京都豊島区にある「グリーンローソン」にて、フィルム型ペロブスカイト太陽電池と電子ペーパーを搭載した電子棚札18個、タブレット端末3台、さらにペロブスカイト太陽電池を搭載した発電パネル3台を設置し、実証実験を行っています。
参照:Saule Technologies
参照:フジプレアム、ペロブスカイト太陽電池で欧企業と協業|メガソーラービジネスplus
ペロブスカイト太陽電池で持続可能なエネルギー供給を
ペロブスカイト太陽電池は、軽くて柔軟性があり、高効率な次世代エネルギー技術として、世界中で注目を集めています。日本でも中小企業や研究機関が力を合わせ、実用化に向けた取り組みが加速しています。
最後に、この記事で押さえておきたい重要ポイントを確認しましょう。
軽量かつ高効率で、建物や車など多様な場所に設置可能な技術である
製造コストが低く、国内材料での生産が可能である
耐久性や鉛問題・量産化などの課題に対して、改良に向けた研究が進んでいる
政府などの支援を受け、2030年からの実用化を目指している
中小企業や大学、自治体が連携することで、新たな事業拡大が期待できる
今後は、企業が自社の強みを活かして、材料開発や印刷装置などの分野に参入するチャンスが広がります。まずは、最新の技術動向を把握し、自社の技術や設備を活かせる分野を見つけることから始めましょう。
『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!











